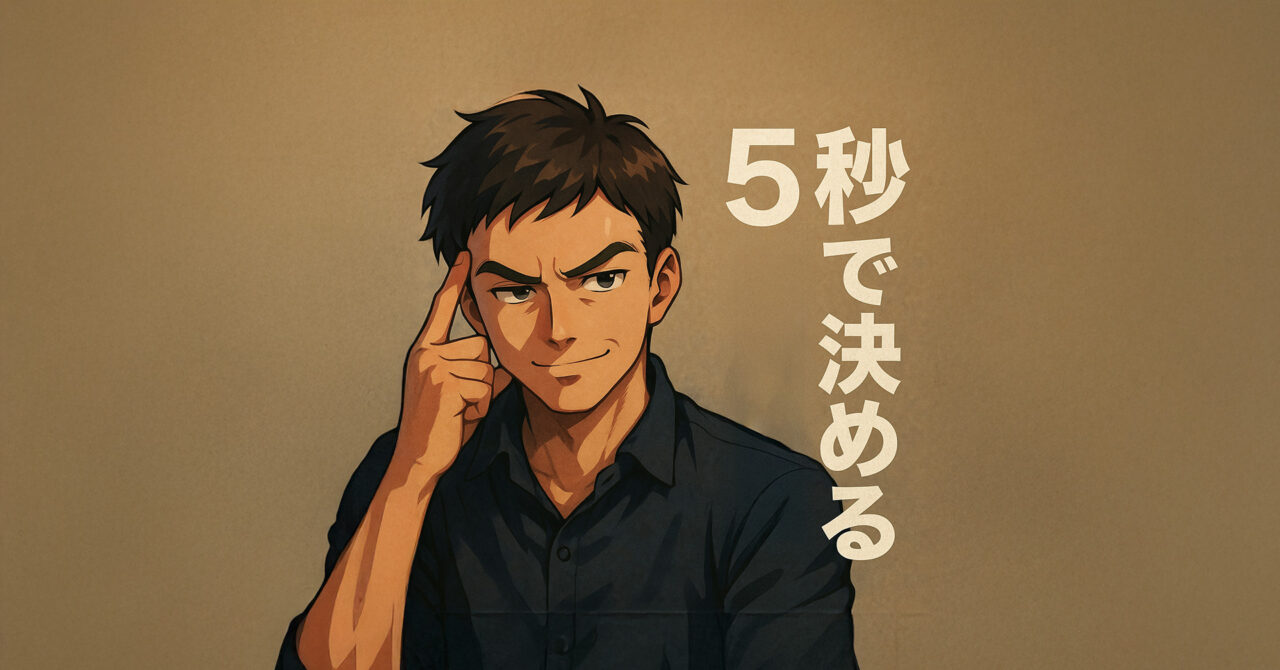こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!
最近はAIの相談に加えて、「どうやって物事を決めるか?」という意思決定に関する話題も増えてきました。
そんな中、SNSでときどき流れてくる名言っぽい短文があります。
「5秒で決めても、30分悩んでも、結果は86%同じ」
……というもの。
これ、なんか気持ちはわかるんですよ。
「迷ってばかりいないで行動しよう」というメッセージ。
確かに、悩んで動けない状態から一歩踏み出すには、こういう言葉って効く。
でもね。
この手の「行動ファースト神話」が、“考えてから動く人”にまでマウントを取り始めると、話が変わってくる。
しかも、これとセットで語られがちな「ファーストチェス理論」──
「初心者がセオリーに縛られず、最善手を打てることがある」ってやつも、
気づけばいつの間にか、
「経験なんか要らない。考えるよりも動け。直感最強!」
みたいな雑な思想を支える根拠になってる。
いや、それってほんとに正しいんですか?
今回は、そういった“気持ちいいけど雑な思考法”にツッコミを入れながら、
「考えることの価値」について、改めてちゃんと掘り下げてみたいと思います。
ファーストチェス理論とは?初心者の一手を美談にしすぎ
「ファーストチェス理論」って言葉、耳ざわりは良い。
チェスを初めてプレイした人が、理論や経験に縛られず、プロも驚くような最善手を打つ──
そんなエピソードが語られる。
これ、聞いたときは確かに「ほぉ〜」ってなる。
初心者の“無垢な視点”を肯定するメッセージって、なんか美しいじゃないですか。
でもね、冷静に言います。
それ、ただのラッキーパンチですからね?
経験者が100回中99回成功するのに対して、初心者の1回の奇跡を取り上げてるだけでしょ?
その“1回”を切り抜いて「初心者すげぇ!」って言い出すのは、統計的にどうなの?って話です。
たまたま当たった一手を「才能」とか「直感」とかで飾り立てて、「考えることの無意味さ」の証拠に使うのは、完全にすり替えです。
しかも厄介なのは、こういう話が「行動ファースト」の文脈で使われること。
「考えるより動け!」
──いやいやいや。
一発屋の偶然を“再現可能な戦略”みたいに扱うなよ。
思考も経験も無視して動くだけなら、
それはもはや“賭け”であって、意思決定じゃない。
「5秒で決めても86%同じ」の嘘くささ
「5秒で決めても、30分考えても、結果は86%同じだった」──このフレーズ、SNSのタイムラインや、自己啓発系の記事で、まるで真理のように語られているのを見かけませんか?
しかも最近は、これが「ファーストチェス理論」とセットで、「ほら、やっぱり深く考えるのは時間の無駄!」「直感に従ってサクサク行動あるのみ!」みたいな、思考停止を加速させるブースターとして使われている気がしてならないんですよ。
で、この“86%理論”。ちょっとでも「ん?」と思ったら、すぐにググってみてください。驚くほど、まともな出典が見つからないはずです。
「スタンフォード大学の最新研究で~」とか、「某有名コンサルタントが提唱していて~」みたいな、それっぽい肩書は出てくるんですが、具体的な論文名、研究者の名前、調査方法、サンプルサイズ……そういった裏付けとなる情報が、まるで都市伝説みたいに存在しないんです。
僕が過去に見た酷い例だと、
- 情報商材系のnote: 「成功者の9割は5秒で決断している!なぜなら脳科学的に~(以下、もっともらしい専門用語の羅列)」みたいな、具体的なデータは一切なし。
- 怪しげなオンラインセミナー: スライドの片隅に小さく「※当社調べ」とだけ書かれたグラフ。比較対象も不明で、一体何をどう調べたのかさっぱり分からない。
- ビジネス系のインフルエンサーの投稿: 「今日、ランチを5秒で決めたら最高に美味しかった!やっぱり直感最強!」みたいな、個人の超主観的な体験を一般論のように語る。
正直言って、この手の数字って、**売らんがための“味付け”**でしかないんですよ。
考えてみてください。
- 権威付けのための海外の有名大学名
- インパクトを与えるための具体的な数字「86%」
- 思考停止を誘う衝撃的な結論「考えるだけ無駄」
これらを適当に組み合わせるだけで、それっぽい雰囲気は簡単に出せるんです。でも、冷静に分析すれば、それはただの言葉のマジックであり、科学的な根拠に基づいた主張とは到底言えません。
そして、一番問題なのは、こういう根拠のない数字を都合よく解釈して、思考停止の免罪符にしてしまう人たちがいること。
「ほら、やっぱり考えすぎるのは損なんだ!」
「だから俺は直感でバンバン決めていくぜ!」
「考える暇があったら動けってことだよ!」
……いやいや、ちょっと待ってくださいよ。それ、**ちゃんと考えて行動している人の“洗練された直感”**を、ただ真似ようとしているだけじゃないですか?
こういう「科学っぽくて気持ちの良い断言」は、思考することを放棄するための、最強の言い訳になりかねません。一度「考えなくても良いんだ」という楽さを知ってしまうと、深く考えることから逃げるようになってしまう。まさに、思考の麻薬です。
だからこそ、僕たちは立ち止まって、この手の安易なメッセージに疑問を持つ必要があると思うんです。「本当にそうなの?」「根拠はあるの?」と。
安易な「行動ファースト」論に流される前に、まずはその根拠となっている情報の信頼性をしっかりと見極めることが大切なのではないでしょうか。
考えるとは何か?行動ファースト論を再考する
「行動がすべて」
「とりあえずやってみよう」
「やりながら考える」
──最近のビジネス界隈では、こういった行動ファースト系の言葉が、まるで成功への万能薬のように語られていますよね。YouTube、X(旧Twitter)、自己啓発本、どこを見ても「とにかく動け!」の大合唱。
もちろん、 初期段階で行動を起こすことの重要性は理解できます。完璧主義に陥って動けなくなるのは、もったいないですから。
でもね、ちょっと立ち止まって考えてみたいんです。その「行動」の質を高めるために、「考える」という行為をないがしろにして良いのでしょうか?
「考える」って、ただボーッとしたり、迷ったりすることとは違います。もっと能動的で、目的を持ったプロセスなんです。それを踏まえた上で、「行動ファースト」論を改めて見つめ直したいと思います。
| 項目 | 「悩む」 | 「考える」 |
|---|---|---|
| 主となる要素 | 感情(不安、迷い、後悔) | 論理、分析、目的意識 |
| 思考の方向性 | 堂々巡り、同じ考えの繰り返し | 目的達成のための道筋探索、構造化 |
| 情報処理 | 感情フィルターによる歪み、過去のネガティブ経験の想起 | 客観的な情報収集と分析、多角的な視点からの検討 |
| エネルギー消費 | 精神的な疲労感が高い | 集中力が必要だが、建設的な成果につながる可能性 |
| 行動との関連性 | 行動を阻害する可能性 | 行動の方向性を定め、質を高める |
| 知識・経験との関連性 | 知識・経験不足から生じやすい、有効な手がかりを見つけられない | 既存の知識・経験を活用し、新たな知識・経験を獲得する |
| 例えるなら | ゴールが見えない迷路をさまよう | 地図を作成し、ルートを設計する |
この表を見ていただければ分かるように、「悩む」と「考える」は全く異なる性質を持っています。単に時間をかけたからといって、建設的な思考が生まれるわけではありません。
「行動ファースト」論が、もしこの表の「悩む」の状態から脱却し、まずは行動を起こすことを促す意図があるのであれば理解できます。
しかし、「考える」という、行動の質を高めるための重要なプロセスを無視したり、軽視したりするようなメッセージは、非常に危険だと僕は思うのです。
なぜなら、「考える」ことこそが、「どこに向かって、どのように行動すべきか」という設計図となるからです。設計図なしに闇雲に動き回っても、望む場所にたどり着ける可能性は低いのではないでしょうか。
直感力を鍛えるには?経験と知識の蓄積がカギ
SNSで「5秒で決めた方が正しい」とか、「考えるより感じろ」みたいな話を見てると、
“直感”って、まるで魔法か第六感みたいに扱われてる気がします。
でも実際には、心理学の世界では直感はちゃんと定義されていて、
しかもその正体は──まったくスピリチュアルじゃないんです。
🧠 カーネマンの「System 1」と「System 2」理論
ノーベル経済学賞を受賞した心理学者、ダニエル・カーネマン。
彼の著書『ファスト&スロー』では、人間の思考をこう分けています:
- System 1(ファスト):直感的で速い思考。無意識、感情、慣れによる判断。
- System 2(スロー):論理的で遅い思考。意識的に集中し、分析を伴う判断。
一見「魔法のように見える直感」も、
実は System 2 で何度も何度も考えたことが、無意識レベルに染み込んだ結果なんです。
つまり──
直感だけでいけるのは、経験と知識がある分野に限られる。
初見の領域で5秒で決めたら、たいてい間違えます(笑)
📌 直感は、圧縮された熟考の産物
プロの料理人が、ひと口で「醤油入れすぎ」と判断できるのは、
何千回も味を見て、考え、修正してきたから。
整備士が、エンジン音ひとつで「ベルト緩んでるな」と言えるのも、
音と故障の因果関係を脳内に地図化してるから。
直感とは、考えた人間だけが持てる“ショートカット”なんです。
初心者がマネしても、それはただの思いつき。
精度もなければ、再現性もない。
💬 「直感が働いた」とすら思ってなかったときの話
先日、うちの息子がバイクを買うことになって、中古車を一緒に探してたんです。
バイク屋さんだと60万円くらいするモデルが、
ヤフオクだと30〜40万円で出ている。
もちろん安いのは魅力。でも──
素人目には、そのバイクの状態が良いのかどうか、見抜くのが難しい。
そこで試しに、ChatGPTに写真を送って相談してみたところ、驚きました。
- 「この部分のサビが気になりますね」
- 「キャブレターの状態をチェックした方が良いです」
- 「この価格帯なら妥当。ただし整備費が別でかかる可能性が高い」
……まるでバイク屋の査定士みたいな回答が返ってきたんです。
それを見たとき、ふと頭に浮かんだのがこれ:
「これ、バイク査定支援ツールとして商品化できるんじゃないか?」
で、周りに話すとこう言われるわけです。
「そういうビジネスの芽にすぐ気づけるの、すごいですよね!」
でもね──
自分では“直感が働いた”なんて思ってないんですよ。
ただ、「あれ?これ使えるかもな」と感じただけ。
どちらかというと、過去の経験と思考のパターンが勝手に反応した感覚に近い。
あとから振り返って「そういえば、あの瞬間、直感が働いてたのかも」と気づいたぐらい。
💬 起業したばかりの人を見ていて思うこと
Room8に最近入会した会員さんで、起業初期の方がいます。
その方と話していて思ったのが、
直感がまだ“経験ベース”じゃないなということ。
よく「僕ってアイデアマンなんです」って言うんですけど、
出てくるアイデアはどれも「世界狙えます!」みたいなスケールだけ大きくて、
肝心の“どうやって実現するか”が抜けている。
もちろん、それが悪いわけじゃない。最初はみんなそうです。
経験値が足りないだけで、いろんな失敗と試行錯誤の中で育っていくものだと思ってます。
ただ、面白いのは──
僕自身は自分のことを「アイデアマン」だなんて思ったこと、一度もないんですよね。
でもなぜか周囲からは、よくこう言われます。
「アイデアの切り口が面白いですよね」
「よくそんなこと思いつきますね」
でも僕からすると、それは“思いついてる”感覚すらない。
- 「この部分、無駄じゃないか?」
- 「困ってる人、いるよね?」
- 「それならこうやって仕組みにできるかも」
……といった思考が、経験の中から勝手に繋がってくるだけなんです。
ビジネスって、アイデアそのものの面白さじゃなくて、
それをどう実現していくかのプロセス設計力が問われる。
直感も同じで、5秒で出せることが偉いんじゃない。
その5秒に何が詰まってるか、が全て。
経験という土壌がなければ、
どんなに派手なアイデアも、どんなにスピード感ある決断も、
全部“思いつき”で終わるんです。
⚠️ 「直感=速い=正しい」は、思考をサボる言い訳にすぎない
速く決めることがカッコいいみたいな風潮、ありますよね。
でも実際には、直感には次のような危険なバイアスが入り込みます:
- ステレオタイプ
- 感情による歪み
- 思い込み(アンカリング)
- “いつものパターン”への依存
- 確証バイアス
カーネマンも繰り返し言ってますが、System 1はミスを自覚できない。
だからこそ、System 2による「点検と補正」が必須なんです。
🧩 だから、結論はこうです:
直感を強くしたければ、とにかく考えろ。とにかく経験しろ。
速く決めたいなら、遅く考える訓練をしておけ。
「5秒で決めても正しい人」になるには、
その5秒に、数百時間分の知識と失敗が詰まってないとダメなんです。
速さはカッコよさじゃない。
深さの副産物なんです。
まとめ|「考える力」が直感の土台をつくる
「5秒で決めても、30分考えても結果は86%同じ」──
こういうフレーズ、なんか気持ちいいですよね。
でもそれ、本当に“考えている人”が使う言葉でしょうか?
直感って、ただのスピードじゃない。
積み重ねた経験と知識が、無意識に形を変えたものです。
つまり、5秒で決められる人と、5秒で思いつく人には、
天と地ほどの差がある。
そして、行動ファーストの時代だからこそ、
考える力・構造化する力・プロセスを描く力が問われている。
アイデアの派手さや、決断の速さじゃなくて、
その裏にある“見えてる地図の精度”がすべてなんです。
思いついたらすぐ行動──それもいい。
でも、「どこに向かってるのか」が見えてなければ、
どれだけ速く走っても、ただの遠回りです。
考えることをなめるな。
考える力こそが、直感を研ぎ澄ます。
その力は、誰にでも手に入る。
時間をかけて、積み重ねればね。