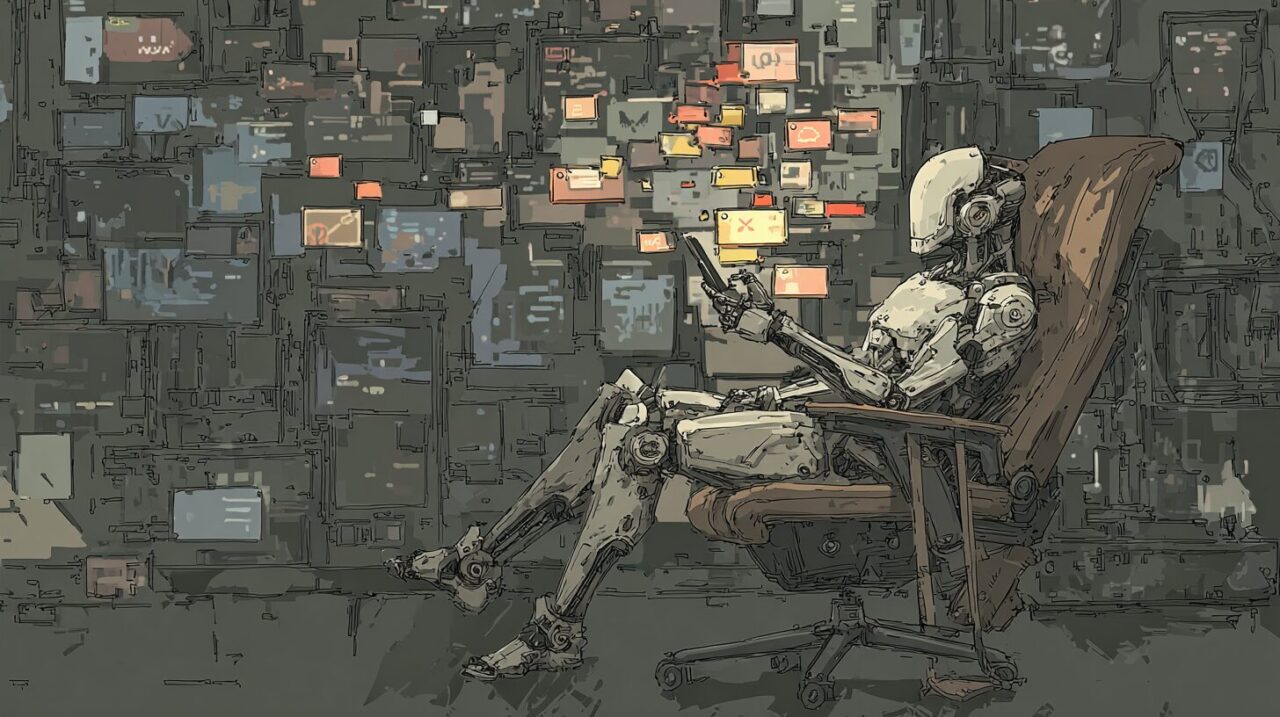最近、「AIって便利ですよね!仕事が楽になりますよね!」って、営業の合間にふんわり言われることが増えてきた。いや、確かにね。便利にはなったよ。でも“楽”って言われるたびに、僕の中のツッコミ担当が椅子から転げ落ちる。
本当に「楽」になってるのか?
「努力の方向」が変わってるだけなんじゃないか?
ChatGPTに聞いたら一瞬で答えが出る?
でも、その「一瞬の答え」にたどり着くためには、結構な回り道と、なかなかのスキルが要る。
Googleの時代は「検索ワード力」だったけど、今は「問いの立て方」そのものが試されてる感じ。
つまり、「AIがあれば楽できる」って思ってる人ほど、逆にしんどくなる。だって、楽するために必要な努力から逃げてるんだから。AIを使いこなすスキルも、仕事のリデザインも、結局ぜんぶ「人間の側の再定義」が求められてるってこと。
今回は、そんな話をちゃんと地に足つけて掘っていきます。
「楽=ノー努力」という勘違いを抱えたままだと、気づいた時には…あれ?僕の仕事どこ行った?ってなるからね。
「知ってる」だけじゃもう足りない。使い方で差がつく時代っぽい
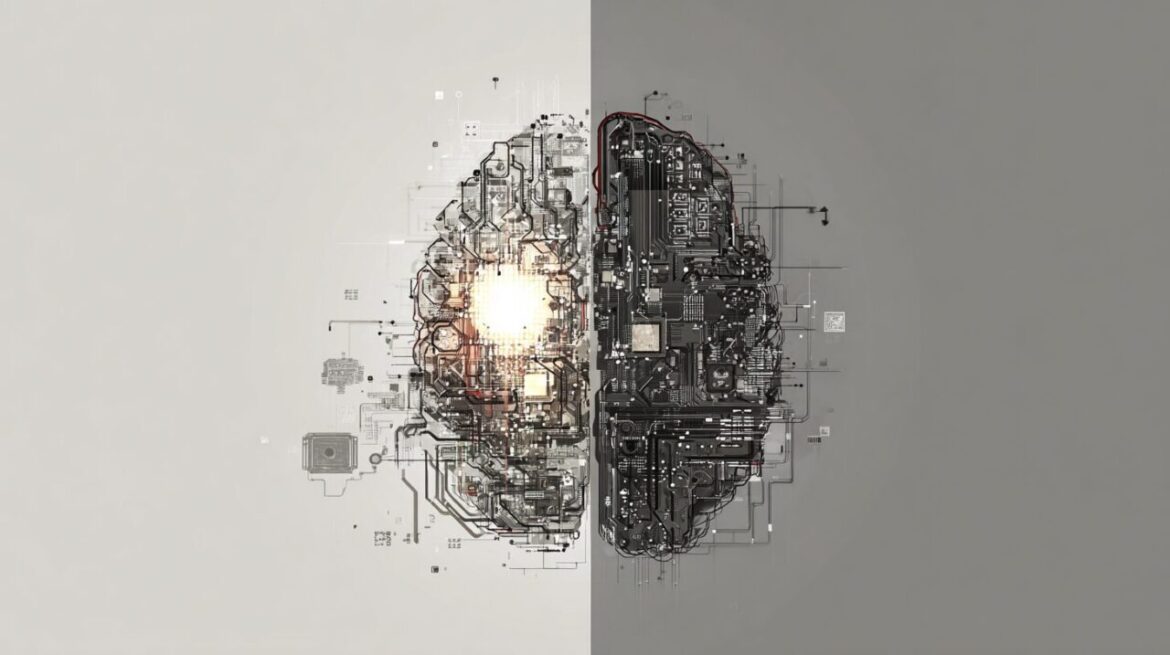
昔は、「知ってる人」が勝ってた。
情報に強い、知識が多い、資格持ってる、それがそのまま“できる人感”になってた。
でも最近、「それ、誰でもAIに聞けば一瞬で出るよね?」って空気がじわじわ広がってきてて。
あれ?じゃあ…今って、“知ってる”ことの価値、ちょっと下がってきてない?って気づく瞬間があるんだよね。
僕も最初は「AIって最高じゃん!答えすぐ出るし!」って浮かれてたけど、ある日気づいた。
「…で、この答え、どうするんだっけ?」っていう新しい沼にハマってることに。
要するに、
- 情報が出てこないことに悩む時代から、
- 情報が“出すぎて選べない”ことに悩む時代へ。
Googleの時代は「検索ワードのセンス」が勝負だった。
でも今は、「そもそも何を聞くべきか」よりも、
「出てきた情報をどう読み取るか・どう活かすか」が本番になってる気がする。
それっぽい答えを並べるのはAIが得意になった。
でも「今この現場、この状況で、この人にとってのベストは何か」って考えるのは、やっぱり人間の役目なんだよね。
…まあ、そこもいずれAIが追いつくかもしれないけど、いまんとこはまだ人間のターン。
だから今、求められてるのは──
「その情報を、どう自分ごとに変換できるか」
「一瞬で出てきた答えを、どう熟成させるか」
…っていう、なんか料理みたいな知性。
つまるところ、答えが速く手に入るようになったぶん、その後の思考と判断が“手抜きできない部分”として浮き彫りになったって感じ。
楽にはなったけど、楽になった“後の自分”に向き合わされるという罠。
ね?便利すぎるのも考えもんだよね。
AIで“楽になる”はずだったのに、なぜか忙しくなっていく問題

AIって、便利なんだよ。マジで。
2年前に比べたら、できることも増えたし、処理スピードも精度も爆上がりしてる。
でも、なんか最近…全然ヒマにならないんだけど?むしろ忙しくなってるんだけど??っていう謎の現象が発生してて。
僕だけ?って思ってたけど、まわりのAIユーザーもだいたい同じ顔してる。
みんな「AIって最高!」って言いながら、タスクの山を前に頭抱えてる。
どういうこと。
理由はたぶんシンプルで、AIが「できること」を増やしてくれたから、やることも勝手に増えてるってやつ。
AIに資料を作ってもらったら、次はそれをもとに別の企画が思いついて、
その企画のたたき台をまたAIに頼んで、
さらにそれを誰かにシェアして…みたいな感じで、勝手に“次の一手”が生まれてくるループに突入。
昔だったら、「そこまでは無理」って諦めてたところが、AIのおかげで「やれちゃう」ようになった。
でも、やれちゃうから「やらなきゃいけない気がしてくる」という呪いが発動する。
そうなるともう、“楽をする”ためにAIを使ってたはずなのに、
結果として「やらなくてもいいこと」まで手を出してるAI奴隷みたいな状態になってくる。
楽になったのに、ヒマにならない。
むしろAIに引きずられて、自分のキャパ以上のことを“気づかないうちに”抱え込んでるという怖さ。
この辺の「やれることが増えた=やるべきことも増えた」って流れ、
ビジネス現場で今まさに進行してる気がする。
便利さの中にある“仕事量のトラップ”、これを見落とすとわりと地獄。
ほんとは「これ、やらなくていいやつだよね?」って切り捨てる勇気が必要なんだけど…
それができる人って意外と少ないし、そもそも何を捨てていいのかすら分からなくなってる。
便利さに飲まれて、迷子になる感じ。ちょっとした現代の風物詩。
楽するために必要なのは、「やらない判断」と「使いこなす自力」

ここまで読んで、「AIって便利だけど、実は怖いな…」って思った人。
安心してください。僕もです。完全に共犯者。
便利なツールが増えた今、求められてるのは「それ、ほんとに今やることか?」って問いを持てるかどうか。
もしくは、AIが出してきた答えに対して、「それ、鵜呑みでいいんだっけ?」って立ち止まる勇気。
つまり、「全部やろう」「全部AIに任せればいい」じゃなくて、
「これはAIに任せる」「これは自分で考える」「これはそもそも捨てる」っていう線引きスキルが、わりと生きる力。
AIをうまく使ってる人って、意外と“全部自動化”してるわけじゃなくて、
“うまく諦める力”とか“人間らしい雑さ”を残してる人だったりする。
全部きっちりやろうとする人ほど、どんどん疲れてる。不思議だけど事実。
あともうひとつ大事なのが、「自分なりに試してみる根性」。
AIのツールって無限にあるし、「これが最適解!」って断言してくれる人も多いけど、
結局のところ、自分の現場にフィットするかは自分で触って試すしかない。
でもね、試すだけなら今はそんなにハードル高くない。
2年前みたいに、呪文のようなプロンプトを書かなくても、
今のAIはわりと察してくれるし、むしろ「ごめん、さっきのもうちょい簡単に言って」って雑にお願いするほうが上手くいくこともある。
楽したいなら、最初にちょっとだけ“自分の癖”を知って、試して、選び取る努力”をしておく。
それさえやっとけば、あとはAIがだいたい何とかしてくれる…かもしれない。たぶん。希望的観測。
AIで“楽”になったはずのブログが、なぜか地味に修羅の道だった話

最初にブログをAIで書いたとき、正直「え、これ30分でできるの?ヤバすぎ!」って思った。
構成も整ってるし、言葉遣いもそれっぽいし、なんなら「もう俺、この調子で毎日書けるんじゃない?」くらいに調子乗ってた。
実際、そのままのテンションで書き続けた。
毎日更新できるし、ラクだし、効率良いし、これは完全に時代を先取りした勝ちパターンでしょ、って。
……が、しばらく続けると気づくんだよね。
「なんか全部、似たようなこと書いてない?」って。
あとから読み返してみると、「うん、普通にいいこと書いてる。けど、どこかで見たような…」って感じ。
で、そこからちょっとずつ違和感が芽生え始めて、
「もっと自分の視点とか、経験とか、突っ込んだ話入れたくない?」ってなってきて、
気づいたらブログ1本に2〜3時間かけてる人間が完成してた。
つまり、AIで“楽をする”つもりが、結果的に“クオリティ中毒”になったんだよね。
気づけば「AIに頼って作業効率UP!」じゃなくて、
「AIを活かして、他にないレベルのブログを作りたい」になってて、
むしろ最初より真面目に文章と向き合ってるという現象。
今、この記事で275本目。
さすがに手慣れてはきたけど、「AIで時間短縮できる=その時間でよりこだわる余地が生まれる」という、なんとも皮肉な真理に行き着いた感じ。
でも、たぶんこれが今のAI活用のリアルだと思ってる。
「手抜きできる」じゃなくて、「こだわりたくなるツールになった」って話。
忙しくなってもいい。でも、AI時代に必要なのは“優先順位センス”かも

ここまで、「AIで楽になるはずが、逆に忙しくなってるんだけど?」って話をしてきたけど、
実は僕、忙しくなること自体は悪いとは思ってないんですよね。
むしろ、やれることが増えて、アイデアも広がって、試せることが山ほど出てくる──
それってわりと楽しいし、創造的な“忙しさ”って、結構幸せなやつなんじゃないかと。
ただ、問題はそこじゃなくて、“何をやるか”の判断が甘いと、全部に手を出して爆発するってこと。
要は「優先順位」。これがズレると、成果も気力も全部ぼやけていく。
例えば僕のブログも、最初は「AI使って毎日更新すればいいでしょ」ってスタンスだったんだけど、
気づいたらクオリティにこだわりだして、時間もエネルギーも投入するようになった。
で、実際どうなったかというと──
昨年9月のアクティブユーザー数が週150人くらいだったのに対して、
今週は1429人。約10倍。
成果、ちゃんと出てる。
でも、その成果を出すために、やることも増えてる。
だから今は、「全部やらない」「やらないことをちゃんと決める」って感覚が、より大事になってきてる。
AIは、可能性を広げてくれる。
でも、それは“選ぶべき道”が増えるという意味でもある。
つまり、AIが増やしてくれた可能性に、こっちが振り回されないようにする力が要る。
使いこなす、ってのは、
AIをすべてに使うことじゃなくて、ちゃんと選んで、捨てるとこ捨てて、深掘りするところを見極めることなんじゃないかなと。
今のところの僕の結論は、そんな感じです。
最後に:AIは楽をくれる。でも、“考えること”は手放せない

AIのおかげで、たしかに僕らは“楽”になった。
でもそれは、“考えなくてもいい”って意味じゃなくて、
“考えるべきことの質と量が変わった”って話なんだと思う。
僕自身、最初は「考えなくてもブログが書ける!」って喜んでた。
30分で1本、効率は最高。でも、ある日ふと気づいたんです。
「そもそも、ブログを書くことが目的じゃなかったよな」って。
伝えること。見てもらうこと。共感してもらうこと。
それが目的だったはずなのに、手段が目的化してたって気づいた。
で、そこから僕のAIの使い方も少しずつ変わっていった。
ただ速くアウトプットするんじゃなくて、どうすれば“届くもの”になるかを考えるようになった。
AIは最高の道具。だけど、使う人間の判断が甘ければ、簡単に「仕事した気になって終わる」ってこともある。
そうならないためには、
・何をやらないか
・どこにこだわるか
・どこで立ち止まるか
このあたりをちゃんと選べる力が必要なんだろうなと。
そして結局、僕がAIで見つけたのは「考えなくていい」じゃなくて、
「本当に考えるべきことって何だったっけ?」って問いに戻る感覚だった。
たぶんこれからも、AIはどんどん便利になっていく。
でも、それに使われるんじゃなくて、ちゃんと主導権を握って、
“自分の目的”に向かって、必要な分だけ付き合っていく。
そのスタンスさえあれば、きっとAIとの付き合い方、間違えないと思う。