こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です。最近は「AIコンサル」なんて名乗って、意味もよく分からずChatGPTを使ってる人たちを横目に、真面目に生成AIを仕事に使い倒す方法を研究してます。
さて、第2回のテーマは──
「意味は無い。だが、それでも」です。
この世界、ちゃんと向き合うとわかります。
矛盾だらけだし、理不尽だし、最終的にみんな死にます。
なのに、SNSでは「意味のある人生を!」って叫ばれてる。
いやいや、ちょっと待って。
本当に“意味”なんてあるんですか?
会社を作っても、いい学校に行っても、結婚しても、子どもを産んでも、全部「そうした方が良さそう」なだけで、意味があるって保証なんかどこにもない。
…それでも僕らは、意味を求めてしまう。
今回は、そんな「意味なんて無い世界で、どうやって生きていくか?」をテーマに、哲学的な話──だけど現実に直結する問い──を扱っていきます。
「意味はない」ことを認めたうえで、それでも「自分で意味をつくる」って、どういうことなのか?
サルトルという偏屈な哲学者を引き合いに出しつつ、今日も虚構と実存のあいだを泳いでいきましょう。
サルトルと実存主義──「意味は後づけでいいんだよ」
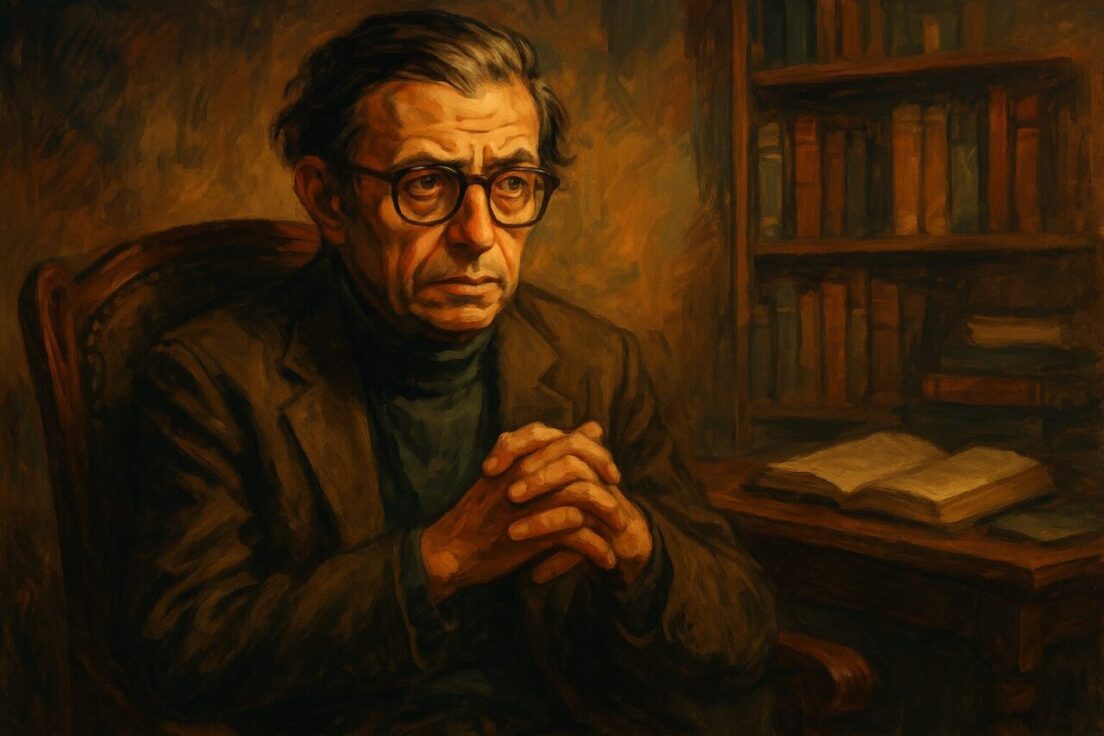
ジャン=ポール・サルトル。
めんどくさい顔して、めんどくさいことを考え続けたフランスの哲学者です。
でもこの人、僕らが「なんか生きる意味って分からんよな……」って夜中にふと思う、あの“気だるさ”に哲学でガチンコ勝負してくれた男なんですよ。
彼の有名な言葉があります。
「実存は本質に先立つ」
……って、はいはい、哲学者ってすぐ難しい言い回し使うんですよね。
でもこれ、めちゃくちゃ大事な話なんです。
それってどういう意味?
簡単に言うと、
「人間は“何者か”として生まれてくるんじゃない。何者かになるって、自分で決めるしかないんだよ」
ってこと。
たとえば、ナイフは「モノを切るため」に作られてますよね。
切るっていう“目的”があって初めてナイフになる。
でも人間はそうじゃない。
意味とか役割なんて、生まれたときは何も決まってない。
人は“あとづけ”で意味をつける生き物
「親を安心させるため」とか
「社会の役に立つため」とか
「成功するため」とか
そういう“後づけの目的”で、なんとか自分の存在を説明しようとしてるだけなんです。
サルトルは、そういう“後づけ”を正面から肯定しました。
意味は最初からあるもんじゃない。あとから、自分でつくるしかない。
それが「自由」であり、同時に「責任」だとも言った。
自由と責任──だから人生はめんどくさい
──は?急に責任?
はい、めんどくさいですよね。でもここが実存主義の肝。
「意味が決まってない=自由」ってことは、 「その意味をしくじったら、お前のせいだよね?」っていう“責任”もついてくる。
だから実存主義って、明るくない。だけどリアルなんですよ。
だって、みんな思ってるでしょ?
「自分って、何のために生きてるんだろう?」
って。
そしてこの問いに対して、
「誰かが答えをくれる」なんて幻想を、サルトルはバッサリ切り捨てたんです。
“自分探し”してる人ほど、迷宮にハマる理由
ちなみにですが──
“本当の自分を探してる”人っていますよね?
旅に出たり、転職したり、スピリチュアルにハマったりして、
「自分らしさを見つけたい」「ほんとうの自分になりたい」って。
でも実存主義的には、こう言われます。
「そもそも“本当の自分”なんて、最初から存在しない」
厳しい話をすると、
「“本当の自分を探してる人”っていうキャラを、自分で演じてるだけだよね?」ってことなんです。
探してる限り、あなたは“探してる人”として人生を消費してる。
それが今の“自分”になってるってだけ。
つまり、
「自分とは何か?」を他人や外の世界に求めてるうちは、 その“求めてる状態”こそが今のあなたの答えってことです。
──はい、逃げられません。
“自由である”って、そういうことです。
でも大丈夫。
この「空っぽな出発点」こそが、
次に話す“虚構”という道具を使いこなすスタートラインなんです。
虚構=自分で選び取る“意味の雛形”
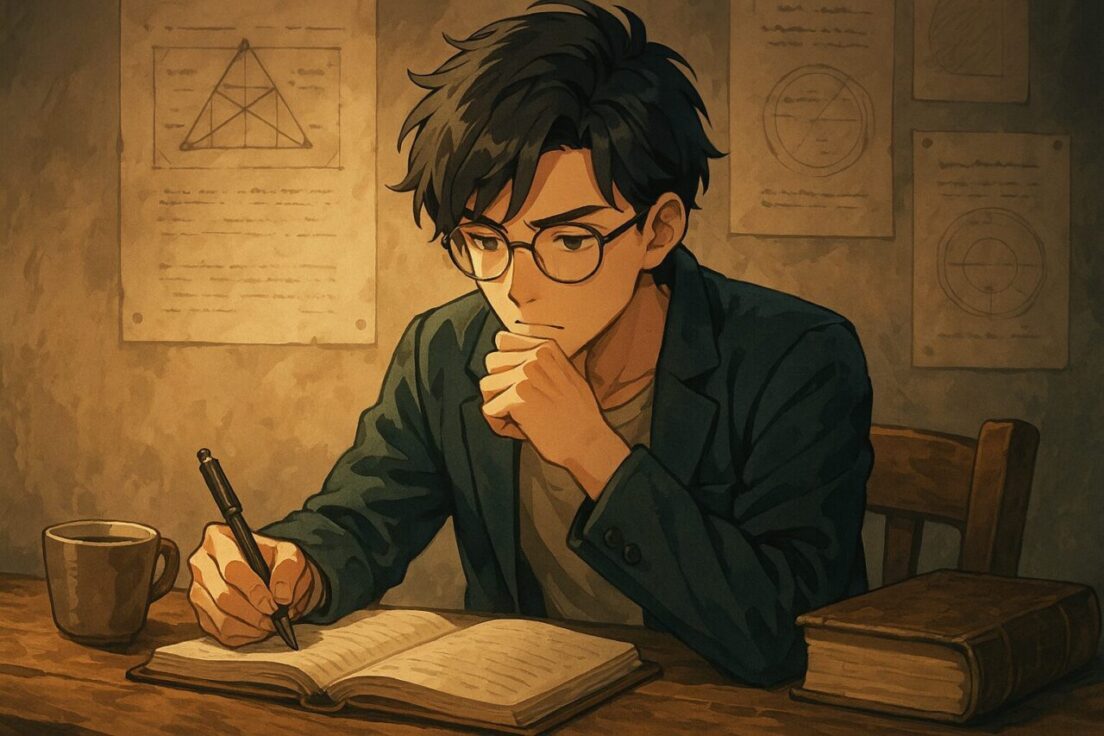
「意味はあとづけ」
「自分でつくるしかない」
──そこまで話したところで、次に出てくるのがこの疑問。
「じゃあ、どんな“意味”をつければいいの?」
これ、迷うのは当然です。
だって、もともと何も決まってない世界なんだから。
ここで登場するのが“虚構”というツール
虚構(フィクション)って聞くと、「嘘」「妄想」みたいなマイナスイメージを持たれることも多いんですが、
ここで言う虚構は、
“みんなが信じることで機能するもの”
のことです。
たとえば、
- 宗教
- 国家
- お金
- 会社
- 学歴
- 倫理
- 理念やビジョン
これ全部、物理的に“そこにある”わけじゃない。
でも、人が信じてるから機能してる。
そして、個人も“虚構”で生きてる
この虚構ってのは、社会だけのものじゃありません。
僕ら一人ひとりも、“信じたい虚構”を自分に与えて生きてるんです。
たとえば、
- 「自分は家族を守る人間だ」
- 「自分はいつか世界を変える起業家だ」
- 「自分はちょっと変わってるアーティスト気質だ」
──これ全部、虚構です。
でも、それを“選んで信じる”ことで、人は前に進める。
虚構=意味の雛形(テンプレート)
意味が無い世界で生きるには、
「これが自分の意味だ」って言い切れる“型”が必要なんです。
でも、その型も、どこかに落ちてるわけじゃない。
作るか、借りるしかない。
だから僕らは、
- 宗教に寄りかかったり
- ロールモデルを真似したり
- SNSでキラキラした誰かの人生を羨んだり
するんです。
そう、それってつまり、
「この人生、こうありたい」というテンプレートを探してる状態なんですよね。
選ぶか、流されるか
虚構を“自分で選ぶ”という行為は、
「自分の人生を、自分で編集する」ってこと。
逆に、虚構を“無意識に信じ込む”とどうなるか。
社会が提示したテンプレにハマり込んで、 気づいたら「誰かの物語の登場人物」になってしまう。
だからこそ、サルトルの「自由と責任」はここでも生きてきます。
何を信じ、どの物語に乗るかは、自分で決めろ。
その代わり、その人生の責任は、お前が持て。
──はい、まためんどくさい。でも、ここを避けるとずっと他人の人生を生きることになります。
生きるためのフィクション──人は虚構なしには進めない
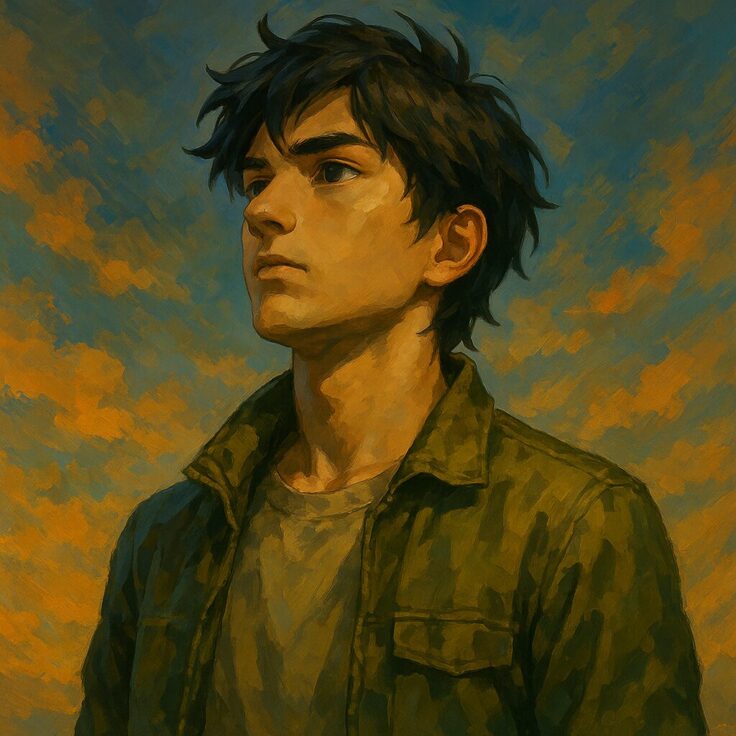
「意味は無い。でも、自分で意味をつくるしかない」
そして、その意味は虚構というテンプレートを“選ぶこと”で形づくられる。
じゃあ、そもそもなんでそんな面倒なことをする必要があるのか?
「意味なんて無いなら、無くてもいいじゃん」って思いますよね。
──でも、それじゃ人は生きていけないんです。
フィクションがなきゃ、前に進めないのが人間
たとえばこんな状況、経験ありませんか?
- 仕事でボロボロに疲れてても「これは家族のためだ」と思えば頑張れる
- 全然うまくいかなくても「これは将来につながってる」と信じれば踏ん張れる
- 今は孤独でも「いつかきっと仲間ができる」と思えば歩き続けられる
──これ全部、“まだ現実になってない未来”への信頼=虚構です。
でも、その虚構があるからこそ人は歩ける。
「ただ生きる」ことはできても、「進む」ことはできない
人間って、ただ寝て食って死ぬだけなら、生きるのは意外と簡単です。
でも、それだけじゃ虚無に飲まれる。
“明日が今日よりマシかもしれない” “この苦しみに意味があるかもしれない”
この“かもしれない”の力が、
僕らを前に進ませてる。
「虚構を信じる知性」こそ、人間の武器
AIは、現実のデータを処理するのは得意だけど、
虚構を“信じる力”は持っていない。
- 神様はいないと分かってても祈る
- 未来は未定だと知ってても目標を立てる
- 幸せの定義なんて無いと分かってても、追い求める
この「分かってるけど、あえて信じる」という行為。
これこそが、人間が“生きる”ための知性なんです。
フィクションを持たない人の末路
もし虚構を一切持たなかったら、人はどうなるか?
- 「どうせ意味なんてない」と言って、無気力に沈む
- 他人がつくった物語に絡め取られて、自分の人生を乗っ取られる
- 「別に何もしたくない」と言いながら、どこか焦燥を感じ続ける
はい、めちゃくちゃ現代っぽい。
むしろ、そうなってる人、周りにめっちゃいません?
だからこそ──
僕らには“信じるに値するフィクション”が必要なんです。
それは宗教でも、理念でも、夢でもいい。
「それを信じる限り、自分は歩ける」って思えるもの。
そしてそのフィクションは、
次のセクションで語るように──
“虚構だと知りながら”信じることができるんです。
矛盾の肯定──虚構と知りながら信じるという知的作為
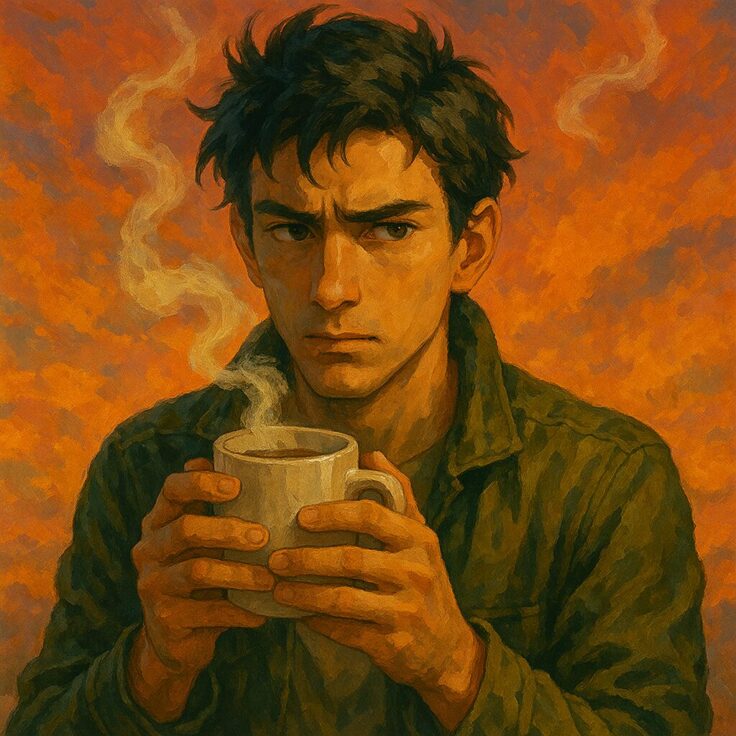
ここまで読んできて、
「いやいや、全部“作りもの”じゃん」って思った人、いるかもしれません。
正解です。
その通り。全部フィクション。
でもね、それを“分かったうえで”信じるって、めちゃくちゃ高度な行為なんですよ。
信じる=本当だと思う、じゃない
普通、信じるって「それが真実だ」と思い込むことだと思われてるけど、
僕らがここで語ってるのは、ちょっと違います。
「これは虚構だと分かってる。 でも、それでも信じてみる」
──この知的でクールな矛盾こそ、人間の可能性なんです。
「自分は特別な人間だ」よりも、コーヒーの方が強い理由
よくいますよね、「本当の自分はもっとすごい」とか「自分は特別な存在なんだ」とか言う人。
でもね、あれめちゃくちゃ抽象的で、薄い。
具体的に何するの?って聞いたら答えられない。
ただの“理想に逃げ込んでるだけ”の虚構の使い方なんですよ。
それよりも、僕がリアルだと感じるのはこういうやつ:
「コーヒーには人を幸せにできる力がある」
……いや、それも虚構ですよ?
科学的根拠なんてないし、どこの論文にも載ってない。
でも、それを本気で信じて、丁寧に一杯ずつコーヒーを淹れてる人がいる。
その行動が、誰かの心をほっとさせて、救ってたりする。
虚構に、行動が追いついたとき“意味”が生まれる
信じることで行動し、 行動が信じていた虚構に“現実味”を与える。
この往復運動の中で、意味が“後づけで”生まれてくる。
だから結局、虚構を信じるってのは、
「世界に意味を与える仕事」なんです。
分かっていて、あえて信じる強さ
今の時代、冷めた目線を持つのは簡単です。
- 「会社なんて幻想だよね」
- 「結婚って制度でしょ?」
- 「SNSの投稿なんて編集された嘘ばっか」
──はい、正論。でもそれだけじゃ前に進めない。
「嘘だと知ってる。でも信じてみる」
その選択をできる人こそが、物語の主導権を持つんです。
それが、僕らが語る「虚構を生きる」という姿勢。
逃げ込むためじゃない。信じて動くために、虚構がある。
そして次回、いよいよ「虚構を編む」リアルな例──
Room8という物語を通じて、それがどう“現実になるか”を語っていきます。
まとめ──虚構を知ることは、自由になること
「意味なんて最初から存在しない」
そう聞くと、ちょっと絶望的に思えるかもしれません。
でも実存主義は、そこから始まる哲学です。
“意味が無いなら、自分で選んでつくればいい”
その選択を助けてくれるのが、虚構という人間だけが持つツール。
宗教でも、理念でも、「コーヒーには人を幸せにする力がある」でもいい。
それが虚構だと知った上で、
あえて信じるという“知的な信仰”こそ、僕らが前に進むエンジンになる。
そしてここで大事なのは、「その虚構をどう使うか?」です。
口だけじゃ意味がない。
虚構に“現実”を与えるのは、信じて動いた人間の行動だけ。
虚構に逃げるのか。
虚構を手に、前に進むのか。
その差が、人生の軌道を決めます。
次回は、「虚構を編む」実例として、
僕が立ち上げたコワーキングスペースRoom8という“物語”を掘り下げていきます。
なぜ僕は「会社という虚構」を作ったのか?
どうやって“誰もいない場所”に意味を与えていったのか?
そして、どうやって他人を巻き込む“フィクションの共犯者”にしていったのか?
そのリアルなプロセスを、全開で語ります。お楽しみに。

