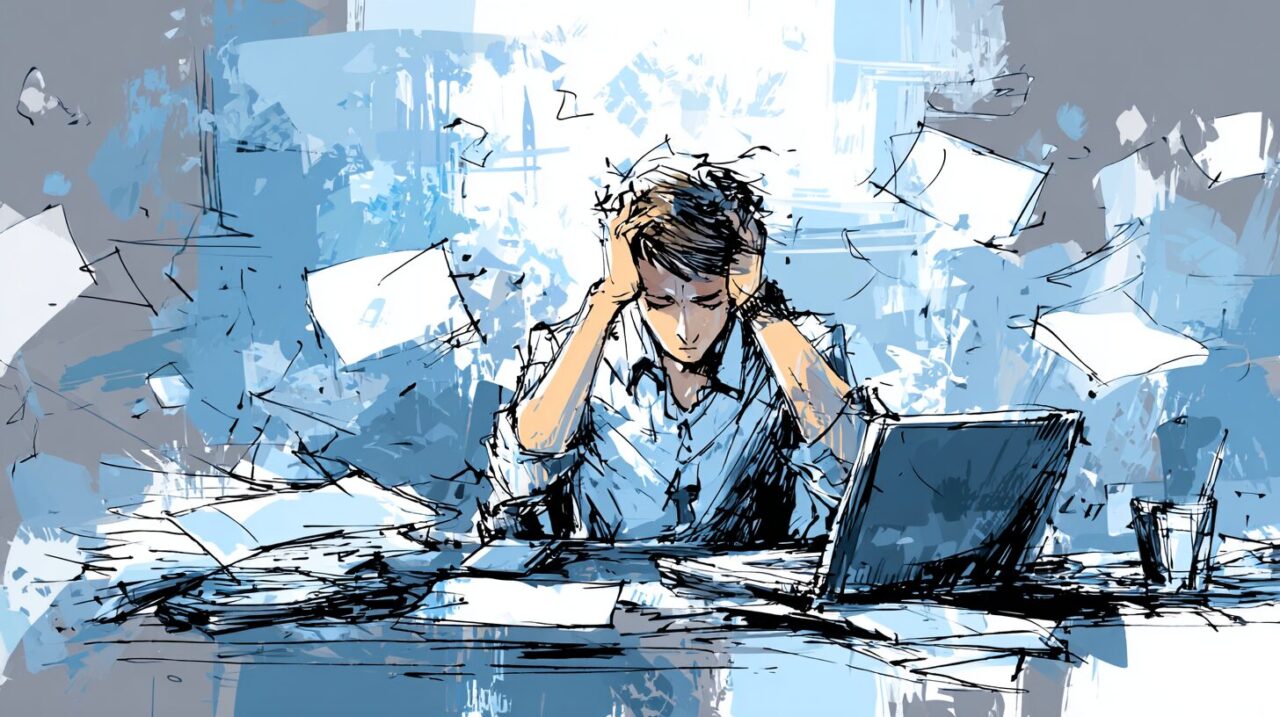こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!
最近、Room8に相談に来る起業家の話を聞いていて、「あー、またこのパターンか」と思うことが増えました。特にWebサイト制作の相談。
「鶴田さん、実はホームページ作ったんですけど、全然お客さん来なくて…」
「制作費が最初の見積もりの倍になっちゃって、もう予算がヤバくて…」
「6ヶ月かけて作ったのに、結局誰にも見てもらえてません…」
僕の元に来る相談の8割が、だいたいこんな感じ。みんな同じところで躓いてる。そして、その失敗パターンって実は5つくらいに集約されるんですよね。
別に僕が特別賢いとか、そういう話じゃない。ただ単純に、同じ失敗事例を何度も何度も見てきただけ。で、「あー、これ事前に知ってたら防げたのに」って思うケースばっかりなんです。
今日は、そんな「起業1年目あるある」のWebサイト制作失敗パターンを5つ紹介します。もしあなたがこれからサイトを作ろうとしてるなら、この記事を読んでから制作会社に連絡した方がいい。マジで。
少なくとも、無駄金50万円と無駄時間6ヶ月は節約できると思います。
失敗パターン1:「プロに作ってもらえば集客できる」勘違い症候群

ビジネスモデル未完成なのに60万投資の悲劇
これ、めちゃくちゃ多い。起業したばっかりで、まだ自分のビジネスモデルもよくわかってない状態なのに、「とりあえずちゃんとしたサイトを作れば、お客さんが来るでしょ」って思い込んでる。
で、60万円とか払って綺麗なサイトを作る。制作会社も「素敵なサイトができました!」って納品してくる。見た目は確かにプロ仕様。
でも、3ヶ月経っても問い合わせゼロ。
「あれ?おかしいな…」
「名刺サイト」に大金かけても誰も来ない現実
問題は、ただの名刺代わりのサイトだったってこと。
- 会社概要、サービス紹介、お問い合わせだけのペラペラサイト
- SEO対策?何それ美味しいの?状態
- 検索しても絶対に見つからない
- 見つかっても「で、何をしてくれるの?」が伝わらない
60万円かけて作った電子パンフレット。それだけ。
マーケティング戦略なしでは無意味
本当に必要なのは:
①どうやってお客さんに見つけてもらうか?(集客戦略)
- SEO対策(これ、日々の運用が必要)
- SNS活用
- 広告戦略
②見つけてもらった後、どうやって成約まで持っていくか?(導線設計)
- 誰に何を売るのか明確化
- お客さんの悩みから解決までのストーリー
- 問い合わせしやすい仕組み
この戦略が固まってない状態で60万円かけても、ただの高級な置き物。
僕がよく言うのは、「サイトは畑、コンテンツは種、SEO対策は水やり」。畑だけ綺麗に作っても、種まかなきゃ何も育たない。
まずは10-20万円の簡単なサイトで始めて、ビジネスモデルが固まってから本格投資。これが正解。
失敗パターン2:「完璧になってから公開」で機会損失地獄

6ヶ月かけて結局まだ未完成の悲劇
「もう少しで完成するので、もう少し待ってください…」
これ、3ヶ月前にも同じこと言ってたやつ。
個人事業主あるあるなんですが、「完璧なサイトができてから公開したい」って思っちゃうんですよね。気持ちはわかる。でも、その間にリアルでお客さんを逃してることに気づいてない。
僕が見た最悪ケースは、サイト制作に1年かけた人。その間、「サイトができたら本格的に営業します」って言い続けて、結局その1年で貯金が底をついて廃業。
サイトは完成したけど、事業は終了。本末転倒すぎる。
「名刺にURL書けない恥ずかしさ」の罠
「まだサイトが中途半端だから、名刺にURL載せられない…」
これもよく聞く話。でも、名刺にURL書けないって、めちゃくちゃ機会損失してますからね。
交流会とか商工会議所のイベントで名刺交換しても、「詳細はWebで」が言えない。相手も「この人、本当にやってるのかな?」って思っちゃう。
80%完成で公開→運用しながら改善が正解
正解は「とりあえず公開」。
- 会社概要、サービス内容、料金、お問い合わせがあれば十分
- デザインは後回し、まずは情報を載せる
- 公開してからお客さんの反応を見て調整
「恥ずかしいサイトでも、ないよりマシ」
実際、僕のRoom8のサイトも最初はショボかった。でも公開してから3年かけて少しずつ改善してる。完璧を待ってたら、今でもサイトなしだったと思う。
お客さんは完璧なサイトを求めてない。求めてるのは「この人に頼んで大丈夫かな?」っていう安心感。
最低限の情報があれば、それで十分。まずは走れ、調整は後で。これがマジで重要。
その間に実際のお客さんと接して、本当に必要な機能がわかってくる。最初から完璧なんて、ありえない。
失敗パターン3:「更新が面倒すぎて放置」サイト化の罠
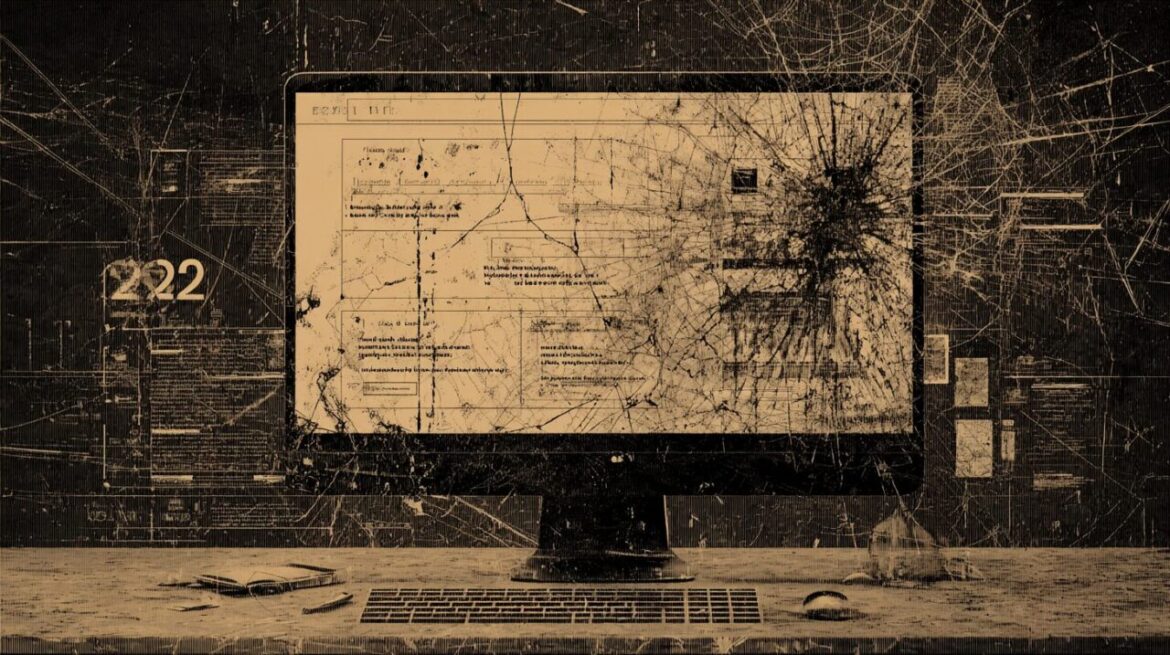
WordPressの管理画面が怖くて触れない
「サイトの情報、ちょっと古くなったから更新したいんですけど…」
よくある相談。で、「じゃあ自分で更新すればいいじゃん」って言うと、
「WordPressの画面がよくわからなくて…触るの怖いんです…」
気持ちはめちゃくちゃわかる。制作会社が作ったWordPressの管理画面って、機能てんこ盛りで初心者には意味不明。
- プラグインが30個くらい入ってる
- メニューが複雑すぎて迷子になる
- 「何かを壊しそう」で触るのが怖い
- バックアップ?何それ?
結果、ちょっとした修正でも毎回制作会社に依頼。1回5,000円とか取られて、「更新するたびにお金かかるのかよ…」ってなる。
「2022年のお知らせ」がトップページに残り続ける地獄
で、更新するのが面倒になって、サイトが時間停止状態になる。
トップページのお知らせ:「2022年4月:ホームページを開設しました」
2025年になってもこれ。お客さんが見たら「この会社、大丈夫?」って思うよね。
僕が見た最悪ケースは、「2021年のコロナ対応について」がずーっとトップに表示されたままの会社。もう3年以上放置。
古い情報が残ってるサイトは信頼性ゼロ。逆効果になってる。
制作会社依存で自分では何もできない状態
さらにヤバいのが、制作会社に完全依存してしまうパターン。
「料金変更したいです」 → 「5,000円です」
「写真差し替えたいです」 → 「3,000円です」
「お知らせ追加したいです」 → 「2,000円です」
月に2-3回更新するだけで15,000円。年間20万円近く更新費用がかかる計算。
「もうサイトなんていらない…」ってなるのも当然。
更新しやすさを最初から設計に組み込むべき
正解は「更新のしやすさ」を最初から重視すること。
制作依頼時に確認すべきポイント:
- 「自分で更新できますか?」
- 「更新方法のレクチャーはありますか?」
- 「管理画面はシンプルにできますか?」
- 「更新マニュアルはもらえますか?」
おすすめは「ペライチ」とか「Wix」とか、最初から更新前提で作られたツール。見た目は少し劣るけど、自分で更新できる方が100倍マシ。
WordPressにするなら、不要なプラグインは全部削除してもらって、本当に必要な機能だけ残してもらう。
サイトは作って終わりじゃない、育てていくもの。更新できないサイトは、最初から作らない方がいい。
失敗パターン4:「あれも出来るこれも出来る」何屋かわからない症候群
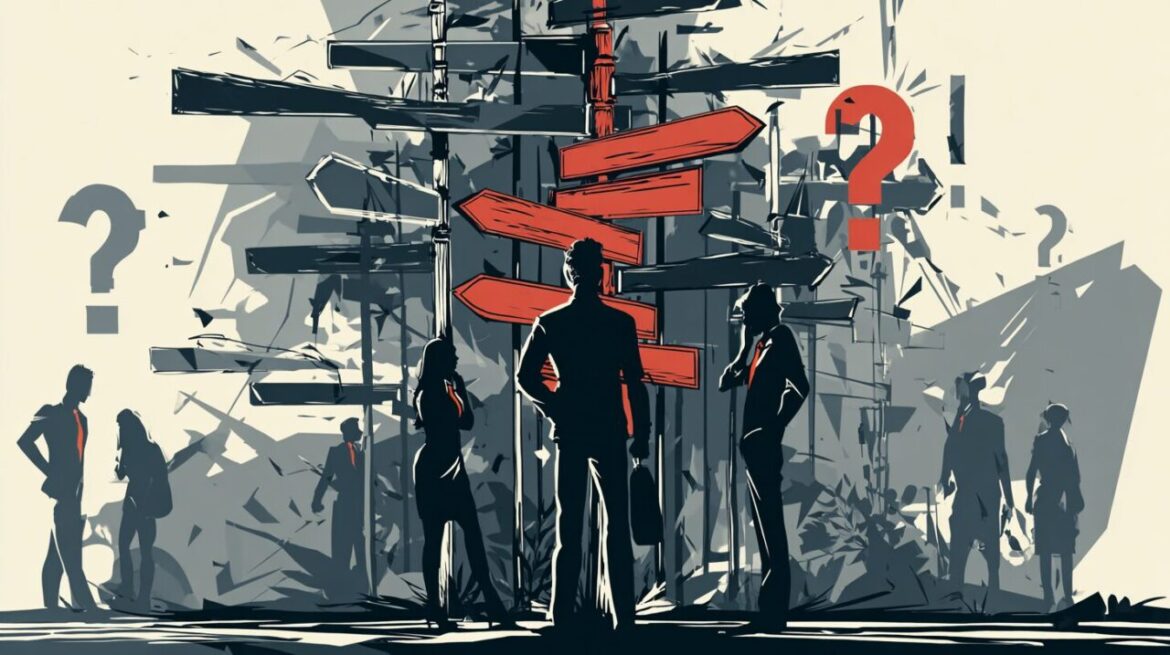
税理士なのにFPも保険も全部やります宣言
先日、うちに相談に来た税理士さんの話。サイトを見せてもらったら、こんな感じでした。
【サービス一覧】
- 税務顧問
- 確定申告
- 相続税対策
- 会社設立
- ファイナンシャルプランナー業務
- 保険相談
- 不動産投資相談
- 経営コンサルティング
「で、結局あなたは何のプロなんですか?」
「えーっと…全部できます…」
それ、全部できるって言ってるけど、全部中途半端に見えますよ。
どこの税理士も同じメニュー表症候群
で、試しに他の税理士のサイトも見てみたら、みんな同じようなサービス一覧。
税理士A:税務・相続・会社設立・FP・保険
税理士B:税務・相続・会社設立・経営相談・保険
税理士C:税務・相続・会社設立・FP・不動産
全部一緒やん。お客さんからしたら「どこに頼んでも同じでしょ」ってなる。
結局、「家から近いところ」「料金が安いところ」で選ばれることになる。完全に価格競争。
「何でも屋さん」は誰からも選ばれない
「うちは何でもできます」って言ってる人ほど、何も任せたくないんですよね。
なぜなら、専門性が感じられないから。
相続で悩んでる人は「相続専門の税理士」に頼みたい。
節税したい人は「節税に強い税理士」に頼みたい。
創業したい人は「創業支援専門の税理士」に頼みたい。
「なんでもやります」の人には、誰も頼みたくない。
強みを1つに絞るとWeb戦略が決まりやすくなる
その税理士さんに聞いたら、実は相続案件が一番得意で実績も多いとのこと。
「じゃあ、『相続専門税理士』で行きましょう」
そうすると、Web戦略が一気に決まる:
- 「相続税 春日井」「相続手続き 愛知」でSEO対策
- ブログは相続関連の情報発信
- お客様の声も相続案件に絞る
- 料金表も相続サービスをメインに
専門性を打ち出すと、運用もしやすくなるし、お客さんにも選ばれやすくなる。
「選択と集中」ができない人が8割
でも、これができない人がめちゃくちゃ多い。
「でも、他のお客さんも逃したくないし…」
「せっかく資格持ってるから活用したいし…」
「売上が減りそうで怖いです…」
逆です。絞り込んだ方が売上上がります。
「相続専門」って言った途端、相続で悩んでる人が集まってくる。で、専門家だから高い料金でも納得してもらえる。
Room8でも最初は「なんでもできるコワーキングスペース」だったけど、今は「起業支援」に特化してる。起業するときに必要なWeb制作、AI活用、補助金サポートなど、起業に必要なものは何でも取り入れてる。
結果、「春日井 起業」で検索すると8位に表示されるようになった。上位は春日井市のサイトや商工会議所、マネーフォワードや弥生会計みたいなビッグな会社。個人事業としてはかなり上位。
絞り込んだから「起業のことならRoom8」って認知されるようになった。AI講演の依頼とかも来るようになったけど、それは副産物。本業は起業家のトータルサポート。
いずれは上位のお役所系サイトも食っていきたいと思ってるけど、とりあえず専門性を絞り込んだ効果は確実に出てる。
器用貧乏より、一点突破。これがWeb集客の基本中の基本。
失敗パターン5:「ペルソナの属性」ばかり気にして「悩み」が曖昧症候群

年齢・職業設定に必死になって肝心の課題が見えない
「ターゲットは35歳、男性、会社員、年収450万円、既婚、子供1人、趣味はゴルフで…」
で、その人の悩みは何ですか?
「えーっと…」
ペルソナ設定で属性ばっかり細かく決めて、肝心の悩み・課題が曖昧なパターン。これ、めちゃくちゃ多い。
年齢35歳と設定したからって、25歳の人や45歳の人には響かないと思ってる?そんなことないでしょ。
悩みが同じなら年齢関係なく響く
Room8の例で言うと、ターゲットは「起業したばかりの人」。想定は30-40代男性だけど、実際には20代の女性も60代の男性も来る。
なぜなら、悩みが同じだから:
- 「集客どうしよう?」
- 「Webサイト必要だよな…」
- 「補助金って使えるの?」
- 「AIってどう活用すればいいの?」
年齢や性別関係なく、起業したばかりの人は全員この悩みを抱えてる。
属性じゃなくて「状況・課題」で考える
重要なのはこっち:
× 「35歳男性会社員年収450万円」(属性)
○ 「起業したばかりで何から手をつけていいかわからない」(状況・課題)
× 「40代主婦パート年収100万円」(属性)
○ 「子育てしながら在宅で収入を得たい」(状況・課題)
属性は悩み探しのヒントでしかない。本当に大切なのは「どんな課題を抱えてるか」。
ブランディングは課題が決まってから調整すればいい
もちろん、男性と女性では響く言葉は違う。デザインの好みも違う。でもそれはコアメッセージが決まってから考えればいい話。
まず「誰のどんな悩みを解決するか」を明確にする。その後で「男性向けなら青系、女性向けならピンク系」とか調整する。
順番を間違えちゃダメ。
「課題・悩み」が明確ならメッセージは勝手に決まる
「起業したばかりで集客に困ってる人」がターゲットなら:
- 「起業1年目でも確実に集客できる方法教えます」
- 「売上ゼロから月30万円達成した実例公開」
- 「個人事業主が最初にやるべきWeb戦略」
刺さるメッセージが自然に出てくる。
「35歳男性年収450万円」だけじゃ、何のメッセージも作れない。
Room8も「起業で困ってる人の悩みを解決する」が軸。年齢や性別は二の次。悩みが明確だから、響くメッセージが作れてる。
ペルソナは属性じゃなくて、悩み・課題で決める。これ、マジで重要。
失敗を避けるための3つの鉄則
鉄則1:ビジネスモデルを固めてから予算を決める
「まずサイトを作って、それから考えよう」は絶対NG。
順番はこう:
- 誰のどんな悩みを解決するか明確化
- どうやってその人に見つけてもらうか戦略立案
- 成約までの流れを設計
- それに必要な最小限の予算を算出
ビジネスモデルが曖昧なうちは10-20万円の簡単なサイトで十分。売上が上がってから本格投資すればいい。
「将来のために」「せっかくだから」は禁句。今必要ないものは今作らない。
鉄則2:80%完成で公開→運用しながら改善
「完璧になってから公開」は機会損失でしかない。
最初に載せるべき情報:
- 何をしている会社・個人か
- どんなサービス・商品か
- 料金はいくらか
- どうやって連絡すればいいか
これだけあればOK。デザインは二の次。
公開してからお客さんの反応を見て調整する。机上の完璧より、現実の改善。
「恥ずかしいサイト」でも「サイトなし」よりマシ。名刺にURL書けないのは致命的。
鉄則3:「選択と集中」で専門性を打ち出す
「あれもこれも」は「何もできない」と同じ。
サービスは1つに絞る:
- 税理士なら「相続専門」
- Web制作なら「個人事業主専門」
- コンサルなら「起業支援専門」
ターゲットも悩み・課題で絞る:
- 年齢・職業の前に「どんな状況の人か」を明確化
- その人たちが抱える共通の課題を特定
- その課題解決に特化したメッセージ作成
専門性があるから高単価でも選ばれる。何でも屋は価格競争に巻き込まれるだけ。
「100人にちょっと好かれる」より「10人に熱烈に愛される」方が強い。
この3つの鉄則を守るだけで、起業1年目のWebサイト制作失敗は8割防げると思います。
Room8では、こういった起業初期のWeb戦略相談も受けてます。同じ失敗を繰り返す起業家を一人でも減らしたいですからね。
FAQ
プロに依頼すれば集客できるのか?
プロに依頼しても、ビジネスモデルが未完成であれば集客は難しいです。集客にはSEO対策やSNS活用、広告戦略などのマーケティング戦略が必要です。名刺代わりのサイトに大金をかけるべきか?
名刺代わりのサイトに大金をかけるのは避けるべきです。まずは10-20万円の簡単なサイトで始め、ビジネスモデルが固まってから本格的な投資を検討するのが賢明です。完璧なサイトを作るまで公開を待つべきか?
完璧を待たずに80%完成で公開し、運用しながら改善するのが良いです。公開してからお客さんの反応を見て調整することで、機会損失を防げます。サイト制作にどれくらいの予算をかけるべきか?
初期段階では10-20万円の予算で簡単なサイトを作り、ビジネスモデルが固まった後に必要に応じて追加投資を検討するのが良いです。公開前に完璧なサイトを目指すべきか?
公開前に完璧を目指すのではなく、まずは必要な情報を揃えて公開し、その後に改善を重ねることが重要です。まとめ

というわけで、起業1年目でやりがちなWebサイト制作の失敗パターン5選をお届けしました。
振り返ると:
- ビジネスモデル未完成で高額投資 → まずは戦略、投資は後で
- 完璧主義で機会損失地獄 → 80%完成で公開、改善は運用しながら
- 更新が面倒で放置サイト化 → 更新しやすさを最初から設計に組み込む
- 「何でも屋」で差別化できない → サービスは1つに絞って専門性を打ち出す
- 属性重視で悩みが曖昧 → ペルソナは課題・状況で決める
全部に共通してるのは「準備不足」。
Webサイトを作る前に、ビジネスモデル、ターゲットの悩み、集客戦略、運用方針を決めておく。これができてれば、ほとんどの失敗は避けられる。
逆に言うと、これができてない状態で制作会社に依頼しても、お金と時間の無駄。制作会社は言われた通りのものを作るだけ。戦略は考えてくれない。
「完璧より完成」「投資より戦略」「属性より悩み」
この3つを覚えておいてください。
もし「うちも同じような失敗をしそう…」って思ったり、「もう失敗しちゃったよ…」って場合は、春日井コワーキングスペースRoom8に相談しに来てください。
起業家同士の情報交換もできるし、同じような失敗をした人たちの体験談も聞けます。一人で悩んでても解決しないことが多いですからね。
失敗は成功の元とは言うけど、避けられる失敗は最初から避けた方がいい。お金も時間も節約できるし、精神的にも楽です。
それでは、賢い起業家ライフをお送りください!