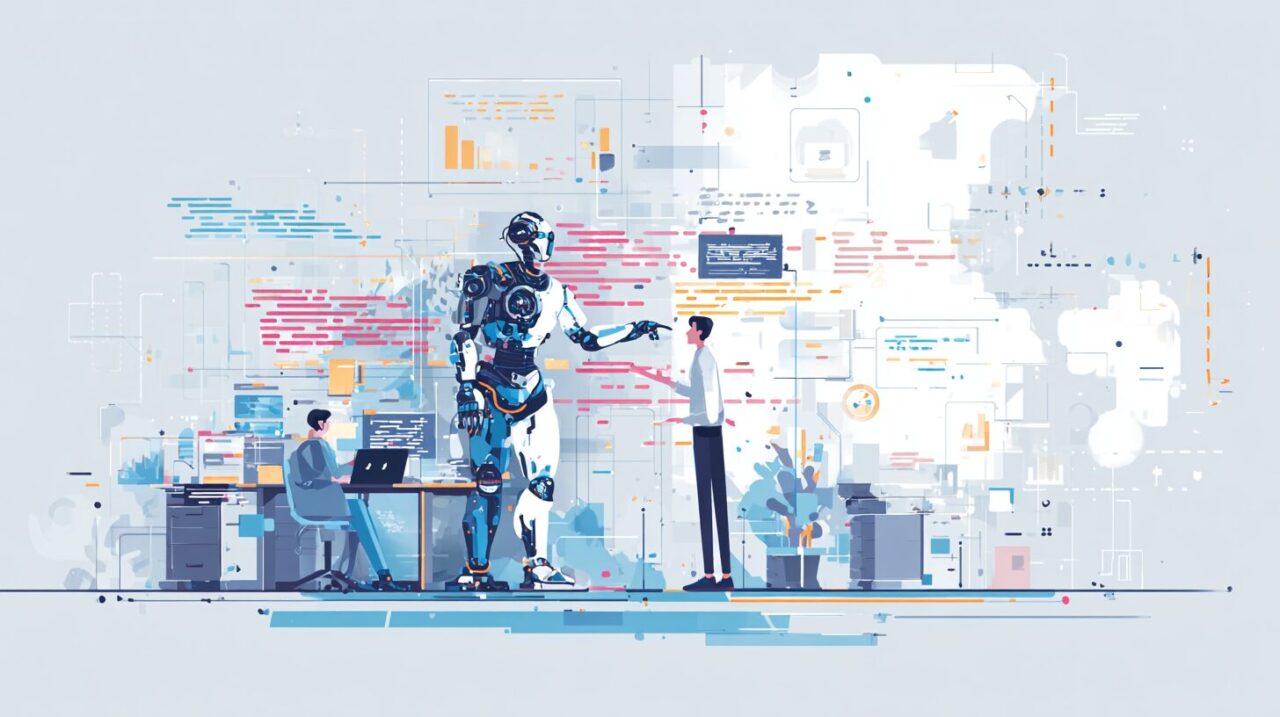こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です。
最近AIの新機能が次から次へと発表されるので、
正直「またか」と思う方も多いのではないでしょうか。
今回の「Codex」も、興味のない方には「エンジニア向けのよく分からない追加機能」にしか見えないかもしれません。
実際、一般のビジネスパーソンでこの話題を追いかけている人はごく少数です。
情報が流れてきても、「また知らない単語が増えただけ」で終わることがほとんどでしょう。
ただ、Codexには今までのAI系アップデートとは少し違うポイントがあります。
自分でプログラムを書けない方でも、“地味で面倒な日々の業務”を自動化したり、
エンジニアに頼んでいたちょっとした修正や新規機能追加を、日本語で指示するだけで実現できる可能性が出てきました。
ChatGPTのCodex機能やCLIについて、
「自分には関係ない」と思っている方ほど、
少しだけ目を通してみても損はない内容です。
ChatGPTとCodexは何が違うのか

ChatGPT(従来)は、いわば“便利なコピペ職人”のような存在です。
「この計算だけやるPythonの関数を書いて」と頼めば、その場で必要なパーツを作ってくれる。
部分的な処理や単発のコード生成が得意で、こちらから「どう書いてほしいか」を細かく指定する必要がありました。
一方でCodexは、「こういうことを自動化したい」「この一連の業務をシステム化したい」と目的をざっくり伝えるだけで、
必要なファイルの作成や、既存コードの修正、新しい連携の組み込みなど、“ゴールに向けてプロジェクト全体をAIが自動で構築していく”イメージです。
たとえば――
「売上CSVを集計してSlackに通知する仕組みがほしい」と伝えれば、
- 必要なスクリプトを自動で生成し、
- 必要ならプロジェクト構成も見直し、
- 既存のコードとの整合性を保ったまま機能を追加、
- さらにテストや修正まで一気に対応
といった流れを“まるごと”任せることができます。
例えるなら、
従来のChatGPTは「便利な部品をその都度手渡してくれる店員」だったのが、 Codexは「目的だけ伝えれば、設計から組み立て、最終テストまで全部やってくれる現場監督」に進化した――そんな感覚です。
Codex CLIって何が違うの?
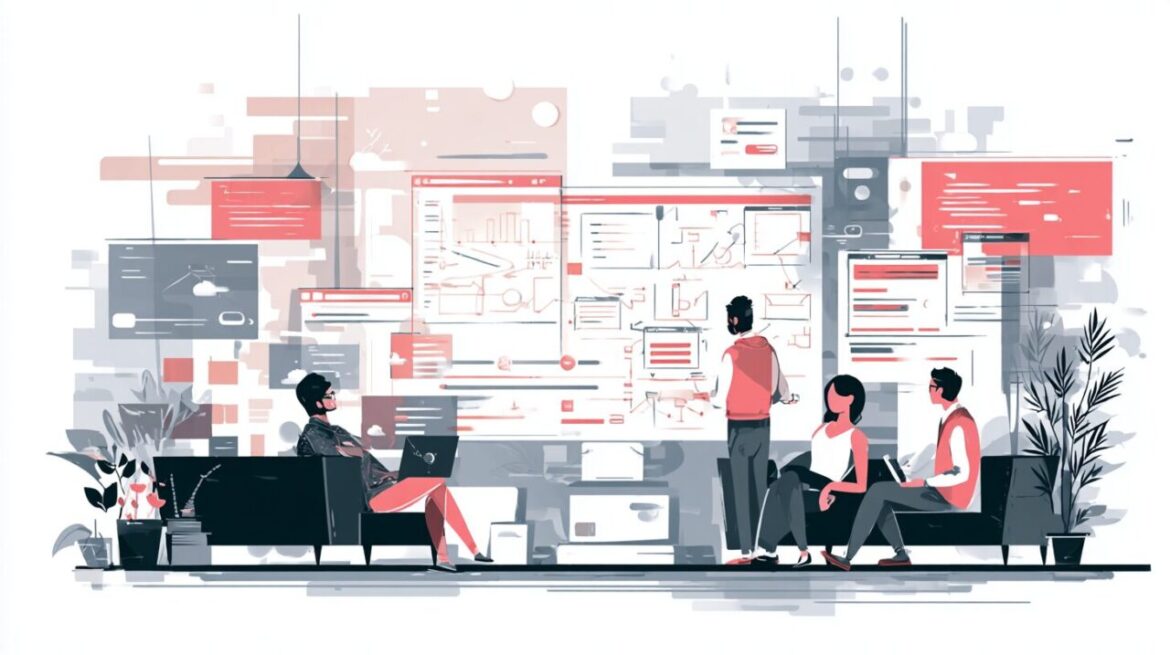
最近よく目にする「Codex CLI」というワードですが、これも「ただの新機能」だと思ってスルーしがちな部分です。
結論から言うと、Codex CLIは「コマンドライン上でAIと対話しながら開発作業を進めるためのツール」です。
普段、ChatGPTの画面から直接「このコードを直して」「こういう機能を追加して」とチャットする人が多いと思いますが、
Codex CLIはPCのターミナル(黒い画面)上で“AI専属アシスタント”と会話しながらコーディングやファイル操作ができるという違いがあります。
たとえば、
- 「main.pyのこのバグ直して」と指示→AIがファイルを自動修正
- 「requirements.txtの依存関係を最新化して」と投げる→AIが自動で追記・整理
- 「テストを走らせてエラーを教えて」と頼めば、AIがテスト実行と診断までやってくれる
といった感じで、
PC上のリアルな開発現場をAIが一緒に歩いてくれるイメージです。
GUI(ブラウザ画面)だと操作の“お膳立て”がしっかりしていて初心者でも使いやすいですが、
CLIは「より自由度高く、細かい作業も全部AIに丸投げできる」反面、
コマンドライン慣れしていない人には少しハードルが高い部分もあります。
本気で「自分の作業現場をAI化したい」人にとっては、CLIが一番頼もしい相棒になるかもしれません。
個人やスモールチームで“今すぐ真似できる”Codex活用法
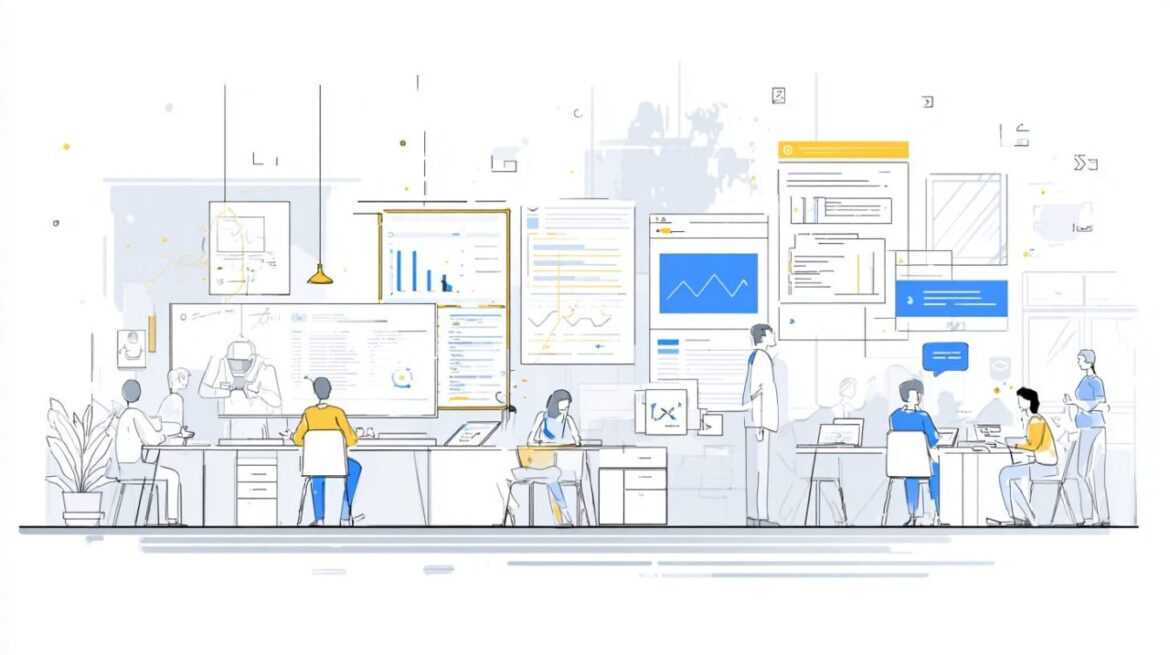
世の中には「大企業のAI導入事例」みたいな話がたくさんありますが、
正直、一般のビジネス現場で参考になることは少ないです。
ここでは、僕たちみたいな小さな事業者や個人でも“明日から真似できる”使い方だけを紹介します。
1. “困ったらAIにまかせる”ホームページ修正アシスト
たとえば「ホームページの色を少し明るくしたい」「自己紹介の内容を変えたい」「新しいお知らせページを作りたい」など、
自分でいじるのは面倒だけど、わざわざ業者に頼むほどでもない“ちょっとした修正”――
これをAIに丸投げできる時代になりました。
やり方は、ホームページのデータを「GitHub」という“ウェブサイトの保管庫”に置いておき、
「ここをこう直して」とAIに日本語で伝えるだけです。
AIは、その指示に合わせて自動で“修正案”を作ってくれます。
この修正案は、「こうしてみたけど、これでいいですか?」という提案書のようなもの。
画面上で内容を確認して「OK」と思えば、そのまま反映できますし、気になるところがあればまたAIに伝えてやり直してもらえます。
2. 日常業務の“地味な自動化”もAIが段取り
たとえば「毎日の売上を自動でまとめて、チャットで報告してほしい」とか、
「Googleフォームの回答をスプレッドシートにまとめて、自動で返信メールも送りたい」など、
普段エクセルやメールで地味に手間がかかっていた作業――
これもAIに仕組み作りを頼めます。
具体的には、集計したいデータ(CSVなど)をGitHubにアップして、
「こういう処理を自動でやって」と日本語で指示。
AIが必要なプログラムや設定を考えて作ってくれるので、
難しいことは一切考えなくて大丈夫です。
3. “オセロ作って”も、普通に通じる
「オセロ」「電卓」など、ルールがハッキリしたゲームやアプリは、
AIがゼロから設計して、プログラム一式を自動で作ってくれます。
「ちょっとカスタマイズしたい」といった追加の要望も、
そのままAIに伝えれば、何度でも修正してくれます。
4. サチコ(Googleサーチコンソール)のデータ分析もAIで
たとえば「GoogleサーチコンソールのCSVデータを使って、どんな検索ワードで自分のサイトが見られているか分析したい」と思ったら、
そのデータをGitHubにアップして、「この内容をグラフにまとめて」「特定の条件で集計して」とAIに頼むだけでOK。
専門的な操作や分析の知識がなくても、“やりたいこと”を伝えるだけで形にしてくれます。
日常業務を“AI現場監督”に丸投げできる感覚
Codexを使うと、
「やりたいこと・困っていること」を日本語で伝えて、
あとはAIが「必要な作業」を全部考えて実行してくれる――
そんな体験が本当に普通にできるようになります。
「便利そうだけど、実際どこまでできるの?」と疑っている方ほど、
とりあえず手元のホームページや身近な業務で一度“お試し”してみると、
AIの変化ぶりが分かるはずです。
まとめ

今回紹介したChatGPTのCodex機能は、
「AIで何でも自動化できる」みたいなバズワードに振り回されがちな世の中で、
珍しく“本当に現場で使える”実用ツールです。
これまでプログラミングは、ごく一部の専門家やエンジニアだけの世界でした。
でも、AIが“自分でコードを書いてくれる”時代になると、
「こんなシステムがあったら便利だな」と思いついた人が、
そのままアイデアだけで実際にツールを形にできる――
そんな未来が本当に見えてきました。
もちろん「すべての作業をAIが魔法のように完璧に片付けてくれる」わけではありません。
それでも、ちょっとした修正や面倒な自動化の段取りを、
AIにまかせて“自分は最小限のチェックだけで済む”世界は、
もう完全に現実のものになりつつあります。
「AIなんて自分には関係ない」と思っている方ほど、
一度くらいは手元の業務やホームページで“AIにやらせてみる”経験をしてみてはいかがでしょうか。
思っているよりも、ずっとあっさり“任せてよかった”と感じるかもしれません。