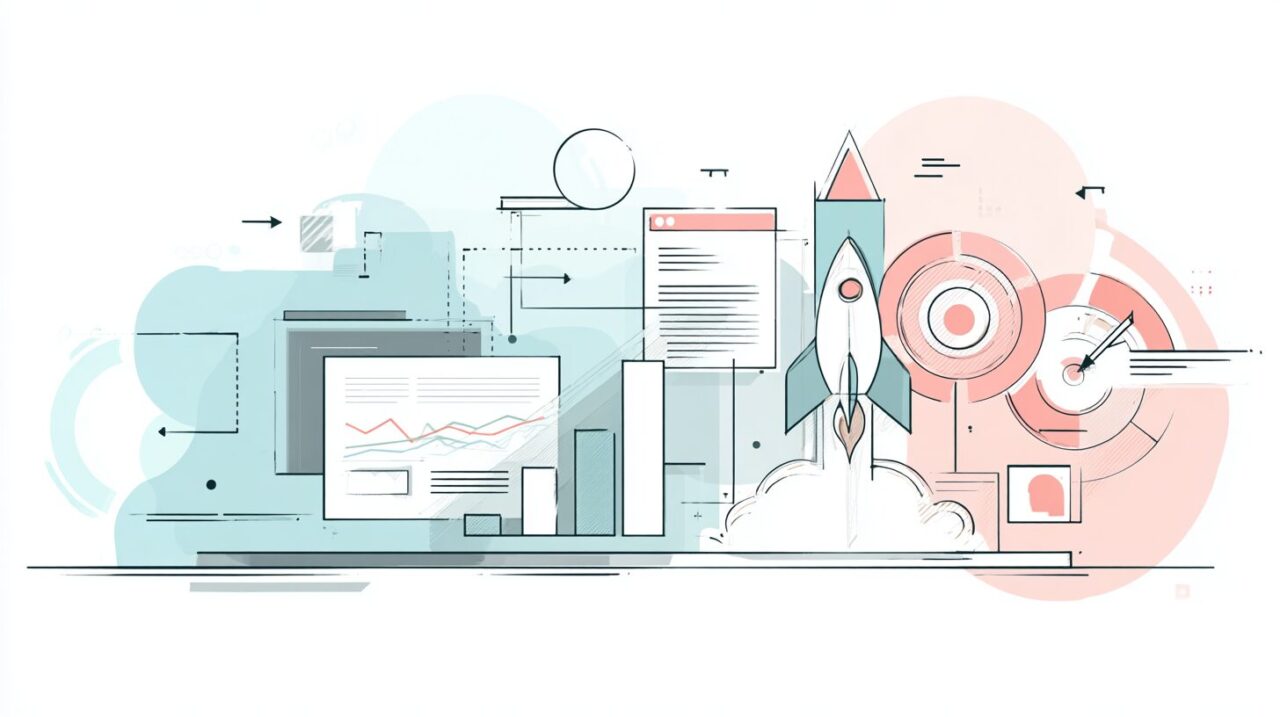こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です。
最近、Room8に起業相談に来る人たちから、テンプレートのように聞く言葉があります。「ビジネスプランをもうちょっと完璧にしてから」「競合調査をもう少し詳しくやってから」「資金をもっと貯めてから」。
要するに、全員が同じ起業セミナーでも受けてきたんですかね。判で押したように同じことを言うんです。
表面的には前向きに聞こえますが、理由を掘り下げていくと、結局は同じところに辿り着きます。失敗への恐怖です。完璧でないものを世に出すことへの不安。まあ、気持ちはわかりますけどね。
実は僕も同じタイプだったりします。Room8の新サービスを追加する時とか、「これでいいじゃん」と思ってても、いざ実行しようとすると妙に抵抗があるんです。最近だとAI講師の依頼が来た時も、頭では「やればいいじゃん」なのに、返事するまでに無駄に悩みました。まあ、結局やりましたけどね。
この「頭ではわかってるのに体が動かない」現象、皆さんにも覚えがあるんじゃないでしょうか。
でも面白いことに、この「完璧主義という名の逃避」って、50年以上前からピーター・ドラッカーが散々警告していたことなんですよね。そして現代のキャリア理論の権威、スタンフォード大学のジョン・クランボルツも、まったく同じ結論に到達している。
つまり、起業セミナーで教わる「失敗回避術」の99%は、学問的に否定された迷信なんです。セミナー講師の大半が起業経験ゼロという現実を考えれば、まあ当然ですが。
ちなみに、このドラッカーシリーズの前回記事では、ドラッカーが現代の起業家に伝えたい3つの真実と現代起業家が誤解しているドラッカーの教えについて書きました。今回はその完結編です。
今日は、起業セミナーでは絶対に教えてくれない、ドラッカーの不都合な真実をお届けします。準備はいいですか?完璧じゃなくても、始めちゃいますよ。
起業準備で陥る完璧主義の罠
起業相談でよく出会う光景があります。100ページのビジネスプランを練り続ける人、競合調査で数ヶ月を費やす人、リスクの洗い出しで身動きが取れなくなる人。
みんな真面目で勉強熱心です。でも共通する問題があります。「完璧になったら始める」と思っていること。
ドラッカーが一貫して警告していたのは、まさにこの「完璧主義という名の行動阻害」でした。
「行動しないことこそが最大のリスクである」。これは、ドラッカーが変化の時代に「機会を逃すことの危険性」を語った文脈から来ています。
また『マネジメント』では「計画は重要だが、実行がなければ意味がない」と明言しています。完璧な計画を追い求めるより、実行して結果を出すことが優先だと。
『イノベーションと起業家精神』でも「イノベーションは、計画されたものではなく、試行錯誤の結果生まれる」と述べています。不完全な一歩でも踏み出すことが大事なんです。
特に注意すべきは、準備期間が長くなればなるほど、市場の変化に取り残されるリスクです。あなたが完璧な計画を練っている間に、競合は新しいサービスをリリースし、顧客のニーズは変化し、市場環境は激変している。
結果として、完璧な計画が完全に無意味になることも珍しくありません。
次に、具体的にどんな「完璧主義の罠」があるのか見ていきましょう。
ビジネスプラン作成で失敗する理由
ドラッカーが指摘した「計画の本質」
「予測は当たらない」「計画は変更されるためにある」「機会は計画の外からやってくる」
これらはドラッカーが実際に言った言葉です。計画は重要ですが、計画通りにいくことの方が稀だということを示しています。
多くの起業家が陥る問題は、計画を目的化してしまうことです。計画は手段であり、実行と修正を繰り返すためのベースラインに過ぎません。
統計が証明する「予測の限界」
スタンフォード大学のジョン・クランボルツが20年間にわたって追跡調査した結果、驚くべき事実が判明しました。成功したキャリアの8割は、予想外の偶然によって決まっている。
どんなに完璧な計画を立てても、成功の要因の大部分は計画外の出来事なんです。この発見は、計画性偶発理論として体系化されています。
成功企業が証明する「計画外」の価値
実例を見てみましょう。
Amazonのジェフ・ベゾス、最初は「オンライン書店」でした。今や何でも売ってるプラットフォームですが、当初のビジネスプランに「クラウドサービス」はありませんでした。AWSは社内インフラを効率化するために作ったシステムが、顧客ニーズと合致して事業化されました。
Twitterは、ポッドキャスト会社の社内コミュニケーション用ツールでした。メインサービスが失敗して、副産物だったツールが世界的サービスになりました。
Room8も最初は単純なコワーキングスペースでした。利用者との対話を重ねる中で、自然とAI相談やセミナー事業が生まれました。当初の計画にはありませんでした。
計画性偶発理論が示す成功要因
クランボルツは、成功の要因として5つの要素を挙げています:好奇心・持続性・柔軟性・楽観性・冒険心。これらは全て「計画を柔軟に修正する能力」に関連しています。
つまり、重要なのは完璧な計画ではなく、変化に対応できる柔軟性なんです。
実行しながら学ぶアプローチ
計画は地図のようなもの。目的地に向かうための参考として使い、途中で道が変わったら躊躇なく修正する。
100ページの詳細な計画を作るより、シンプルな計画で早く始めて、顧客の反応を見ながら調整していく。現代のビジネス環境では、これが最も現実的なアプローチです。
分析に時間をかけすぎる危険性
分析が目的化する典型パターン
Room8での起業相談で頻繁に聞く言葉があります。「もう少し分析してから」
競合調査、市場分析、業界研究、トレンド調査…。どれも大切に見えますが、多くの場合、分析が目的化してしまっている状態です。
典型的なパターンがこれです:
- 競合のサービスを調べる
- 「市場規模も見なきゃ」
- 「業界動向も重要だ」
- 「海外事例も参考にしよう」
- 「専門レポートも読まなきゃ」
- 気がつけば数ヶ月経過
この間に何が起きているかというと、市場は変化し続け、競合は新しいサービスをリリースし、機会は他の誰かに取られているんです。
2500年前から変わらない真理
「巧遅は拙速に如かず」
孫子が2500年前に言ったこの言葉は、現代のビジネスでも全く変わらない真理です。完璧で遅いより、不完全でも早い方が価値がある。
ドラッカーも現代で同じ警告をしていました。『イノベーションと起業家精神』では「イノベーションは、計画されたものではなく、試行錯誤の結果生まれる」と述べています。
つまり、完璧な分析より不完全な実行。これが古今東西の成功法則なんです。
分析している間に機会は逃げる
分析に時間をかけすぎる最大の問題は、機会損失です。
あなたが完璧な市場分析をしている間に:
- 競合は新しいサービスをリリースしている
- 顧客のニーズは変化している
- 市場環境は激変している
- 他の起業家が同じアイデアで先行している
結果として、どんなに完璧な分析も意味がなくなります。
実行しながら学ぶアプローチ
Room8も最初から完璧な分析をしたわけではありません。「春日井でこういう場所があったらいいな」という漠然としたアイデアから始めて、実際に運営しながら形を作っていきました。
AI講師の依頼が来た時も、詳細な市場分析なんてしませんでした。「やってみよう」で始めて、実際の反応を見ながら改善していっただけです。
分析の正しい使い方
分析が不要というわけではありません。問題は時間のかけ方と優先順位です。
推奨アプローチ:
- 最低限の分析で全体像を把握
- すぐに実行開始
- 実行しながら継続的に調整
『マネジメント』でドラッカーが言った通り「計画は重要だが、実行がなければ意味がない」のです。
分析に1ヶ月かけるなら、1週間で概要を把握して、残り3週間は実行に充ててください。その方がよっぽど価値のあるデータと経験が得られます。
起業成功の秘訣は試行錯誤にある
成功の本質は試行錯誤にある
成功に必要なのは試行錯誤です。一見華々しく大成功していて失敗など遠い存在のように思える、有名な起業家でも、その成功の裏には無数の失敗を抱えていることが殆ど。
つまり10回失敗して1回成功しているみたいなことが殆どで、これが成功者のパターンです(10回かどうかは置いといて、あるいはもっと多くの失敗かもしれません)。
ドラッカーが『イノベーションと起業家精神』で指摘していたのは、まさにこの点でした。「イノベーションは、計画されたものではなく、試行錯誤の結果生まれる」
好きな人へのプレゼント選びと同じ構造
これって、好きな人へのプレゼント選びと同じ構造なんです。
分析型のアプローチ:
- 相手の好みを徹底的にリサーチ
- SNSを遡って好きなブランドを調査
- 友達にヒアリング
- 完璧なプレゼントを選ぶまで何ヶ月も悩む
- 結果:もう既に持ってた、どんだけ考えても計画通りには行かない
試行錯誤型のアプローチ:
- とりあえず小さなプレゼントをしてみる
- 反応を見る
- 喜ばれたら同じ方向性で次を考える
- ダメだったら違うアプローチを試す
- 結果:相手の好みがリアルタイムで分かる
どちらが相手の本当の好みを知れるでしょうか?圧倒的に後者ですよね。
そして重要なのは、相手を喜ばせるのって一発勝負じゃないことです。プレゼントが喜ばれないことはあっても、それで嫌われることはない。むしろ「考えてくれてる」ことが伝わります。ダメだったら次があるから、安心して試せる。当たりを探していけばいいだけです。
ビジネスでも全く同じ構造
「この商品は売れるだろうか?」
この問いに対する答えを得る方法も2つあります:
分析アプローチ:
- 市場調査を数ヶ月
- 競合分析を詳細に
- 顧客インタビューを重ねる
- 完璧な商品を作り上げる
試行錯誤アプローチ:
- とりあえず最小限の商品を作る
- 実際に売ってみる
- 市場の反応を見る
- 反応に応じて修正する
どちらが正確な答えを得られるでしょうか?圧倒的に後者です。
ビジネスでも一発勝負じゃありません。小さく始めれば、失敗しても致命傷にはならない。失敗してもやり直せるし、良い商品を作れば売れる。だから安心して試行錯誤しましょう!
市場が教えてくれる真実
市場の反応が一番正確な「分析結果」なんです。
どんなに完璧な市場調査をしても、実際に売ってみないとわからないことが山ほどあります:
- 本当に顧客が価値を感じるか
- 適正な価格はいくらか
- どんな改善が必要か
- 想定外のニーズはないか
Room8のAI関連事業も、最初の計画は、最初はブログを書いてSEOを上げて、コンサルを受けたい人が問い合わせしてくる計画でした。
ところが実際には、コンサル依頼ではなく講師依頼が来ました。その講師依頼を受けたことで別の講師依頼も来て、「講師を挟んだ方がコンサルに繋がりやすいかな」と計画を修正しました。
これがまさに計画性偶発理論です。AI分野で準備していたからこそ、予想外の講師依頼を活かして、最終的に本命のコンサル事業により良いルートを見つけることができた。
結果重視の改善サイクル
重要なのは「早く始める」ことではありません。「結果を見て継続的に改善する」ことです。
ドラッカーが『マネジメント』で一貫して主張していたのは、成果主義でした。どんなに良いアイデアでも、結果が出なければ意味がない。
効果的な改善サイクル:
- 小さく始める:致命傷にならない規模で
- 結果を測定する:数字で客観的に評価
- 原因を分析する:なぜその結果になったのか
- 改善策を実行:具体的なアクションを取る
- 再び結果を測定:改善効果を確認
このサイクルを高速で回すことで、最初は「不完璧」だったものが、最終的に「完璧」に近づいていきます。
実行して結果から学ぶ
Room8も最初から完璧だったわけではありません。利用者の反応を見て、サービスを少しずつ改善し、新しいニーズに応えて事業を拡大してきました。結果が全てを教えてくれます。
ドラッカーが本当に言いたかったのは「分析して完璧にするより、実際に試して結果から学べ」ということです。
市場は最高の先生です。分析に時間をかけるより、市場に聞いて、その答えをもとに改善を重ねてください。
まとめ:知識を行動に変えよ
ドラッカーの真のメッセージ
今回お伝えした3つのポイントを振り返ってみましょう。
1. 起業準備で陥る完璧主義の罠
「行動しないことこそが最大のリスク」。準備という名の現実逃避に陥っている間に、市場は変化し、機会は他の誰かに取られていきます。
2. ビジネスプラン作成で失敗する理由
「予測は当たらない」「計画は変更されるためにある」。クランボルツの研究でも証明された通り、成功の8割は偶然です。完璧な計画より、柔軟な実行力が勝負を決めます。
3. 起業成功の秘訣は試行錯誤にある
「イノベーションは試行錯誤の結果生まれる」。10回失敗して1回成功、これが本当の成功者のパターンです。分析より実践、計画より検証。
50年変わらない普遍的な真理
面白いことに、これらの教訓は50年前のドラッカーの時代から変わっていません。むしろ、変化のスピードが加速した現代では、その重要性がさらに増しています。
ドラッカーが『マネジメント』で言った「知識は行動によってのみ価値を持つ」という言葉が、すべてを物語っています。
起業セミナーで教わる「失敗回避術」の99%は、時代遅れの迷信です。本当に必要なのは、知識を行動に変える実行力。そして、結果から学んで改善し続ける成果主義です。
実際にやってみて分かったこと
僕自身、効率を重視するタイプです。楽したいというか、無駄な行動はしたくない。「行動して失敗したら時間が無駄になりそう」みたいに考えがちなんです。新しいサービスを始める時も「本当に客ふえるか?」と躊躇してしまう。
でも、実際に動いてみると、「分析してる時間の方がよっぽど無駄だった」と気づくんです。やればすぐに分かる事を時間掛けて分析するので。
AI講師の依頼が来た時も、詳細な準備なんてしませんでした。「やってみよう」で始めて、今では重要な事業の一部になっています。
準備された偶然を掴むために必要なのは、完璧な計画ではありません。適度な準備と、機会を掴む実行力です。
成果こそが全て
でも、ここで勘違いしてはいけません。ドラッカーが言う「成果」とは、「良い結果を出すこと」ではありません。
成果とは、良い結果も悪い結果も含めて「成果」です。成功も失敗も、どちらも価値のある成果。成功からは「何がうまくいったか」を学び、失敗からは「何がダメだったか」を学ぶ。
そして、その成果は市場にあります。分析や計画からは仮説しか得られませんが、市場に行けば必ず成果(結果)が返ってきます。
唯一無価値なのは、何もしないこと。行動しなければ市場からの成果が得られず、学習材料がゼロになってしまいます。
関連記事:
Spring8コワーキングスペースRoom8について詳しくは:
https://www.room8.co.jp/
このシリーズの他の記事や起業・AI活用のヒントは:
https://note.com/room8inc