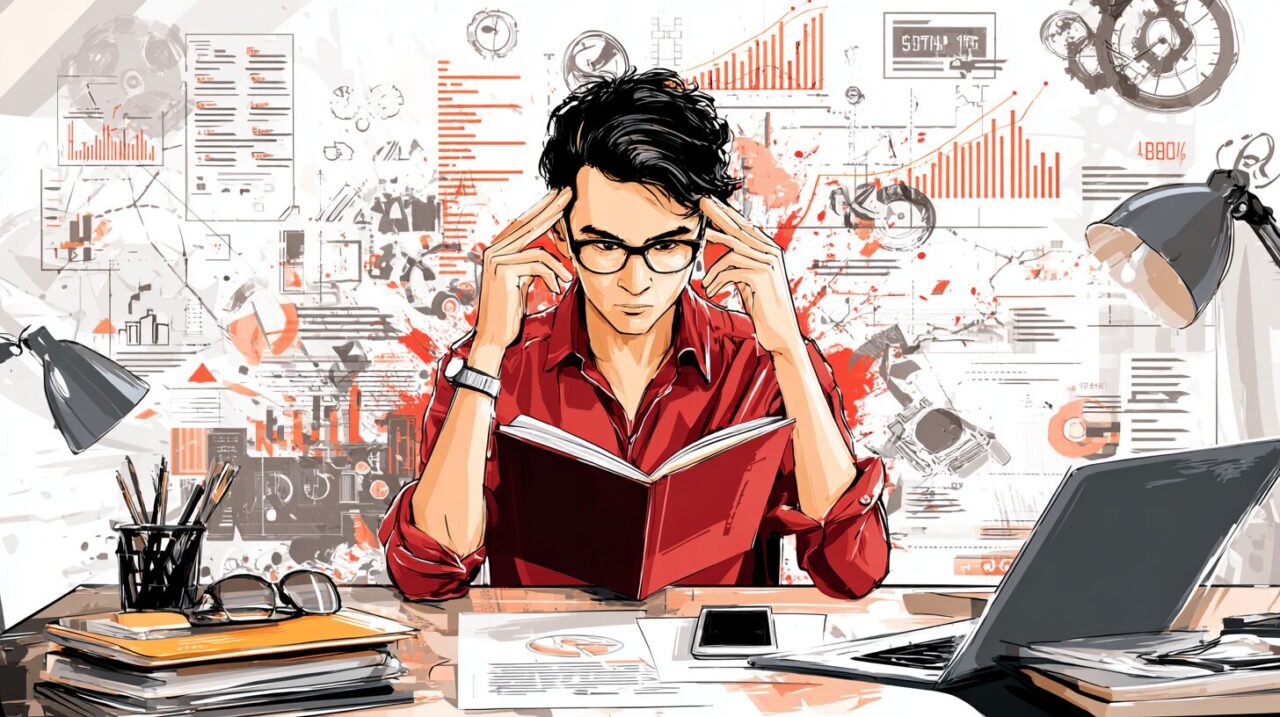こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!最近、地元の起業相談でマーケティングの話をすることが増えてきました。で、みんな真面目にコトラーの本とか読んでるんですよ。「4Pを理解しました」「STPもバッチリです」って。
でもね、実際に事業を始めてみると「あれ?理論通りにやってるのに全然売れない」「ターゲティングもちゃんとやったのに反応がない」って相談が後を絶たない。
「俺の理解が浅いのかな?」「やり方が間違ってるのかな?」って悩んでる人を見てると、いやいやちょっと待てよと。問題はあなたの理解力じゃない。そもそもコトラー理論が想定してる「前提条件」と、現代の零細企業が置かれてる現実が根本的に違うんですよ。
特に「ターゲティング」なんて、同じ言葉を使ってても、1960年代と2025年では意味が180度違う。当時は「効率化のため」に絞ってたのに、今は「生き残るため」に絞らなきゃいけない。
そりゃうまくいかないって話です。
今日は、なぜ多くの真面目な起業家がマーケティング理論にハマって現実とのギャップに苦しむのか、そして現代の零細企業が本当に使える形に理論をアップデートする方法について話していきます。
理論は道具です。神様じゃない。使い方を間違えたら、どんなに立派な道具でも役に立ちませんからね。
コトラー理論が生まれた「作れば売れる」時代
まず理解しておかなきゃいけないのは、コトラーのマーケティング理論が体系化された1960年代って、どんな時代だったかってことです。
戦後復興から高度経済成長期。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、自動車…まさに「作れば売れる」時代でした。消費者は新しい商品に飢えてて、企業の課題は「どう売るか」じゃなく「どうやって大量生産して、効率的に大量販売するか」だったんです。
だから当時のマーケティング理論は、売上を上げることよりも「効率化」に重点が置かれてる。
4Pの枠組み自体は今でも基本中の基本です。Product、Price、Place、Promotionって4つの要素を考えるのは変わらない。でも、その「考え方」「アプローチ」が根本的に違うんですよ。
1960年代の4P(効率化思考):
- Product: 大量生産に適した標準化商品をどう作るか
- Price: 大量生産コスト削減を前提とした価格をどう設定するか
- Place: 全国規模の効率的な流通網をどう構築するか
- Promotion: マスメディアで大量宣伝をどう効率化するか
全部「どうやって効率的に大量に売るか」って発想ですよね。
ターゲティングにしても、「細かく絞って売上を確保する」んじゃなく「広告費を効率的に使うために絞る」「流通コストを下げるために絞る」って考え方。市場全体が伸びてるから、どこを攻めても売れるのは前提だった。
つまり、コトラー理論の根底には「成長期の論理」が流れてるんです。そりゃそうですよ、成長期に作られた理論なんだから。
現代零細企業の現実:「生き残るため」の戦い
一方、2025年の現実はどうでしょうか。
モノが溢れかえって、消費者は選び放題。大企業は大量生産・低価格で攻めてくるし、ネットでは世界中の商品と比較される。「作れば売れる」なんて時代は、とっくに終わってます。
現代の零細企業が直面してる課題は「どうやって効率的に売るか」じゃない。「そもそもどうやって生き残るか」です。
だから、同じ4Pでも考え方が根本的に変わる。
でもここで重要なのは、これは「零細企業の場合」だってこと。大企業には大企業なりの現代版4Pがあるわけです。
大企業の4P(現代版):
- Product: 幅広いニーズに対応できる商品ラインアップ
- Price: スケールメリットを活かした競争力ある価格設定
- Place: 全方位チャネル展開(リアル・ネット・B2B等)
- Promotion: ブランド力とリーチ力でマス訴求
零細企業の4P(現代版):
- Product: 大企業が手を出さないニッチ特化
- Price: 生存ラインギリギリでも顧客価値最大化
- Place: 大企業が来ない小さな勝てる土俵
- Promotion: 限られた予算で深いファン獲得
完全にランチェスターの強者戦略vs弱者戦略ですよね。
だから零細企業が大企業向けの4P理論をそのまま使おうとすると破綻する。「全方位展開」なんて体力的に無理だし、「マス訴求」なんて予算的に不可能。
特にターゲティングなんて、もう「効率化」の話じゃない。零細企業にとっては「勝てる場所を見つける」「限られたリソースを一点集中する」「大企業が『採算合わない』って諦める領域を狙う」っていう、完全に生存戦略です。
でも、多くの起業家は1960年代の「効率化思考」で現代の4Pを考えようとする。そりゃ現実とのギャップに苦しみますよ。時代も事業規模も違うんだから。
大企業が手を出さない「超ニッチ」こそ零細の勝機
これ、面白い事例があるんですよ。
町工場でオースチンミニやスバル360をEV化してる職人がいるんです。「クラシックカーの見た目は保ちつつ、現代の環境性能も欲しい」っていう、めちゃくちゃニッチな需要に応えてる。
トヨタやホンダが、こんな仕事やると思います?絶対やらないですよね。市場規模が小さすぎて、投資対効果が合わない。「スバル360のEV化なんて、年間何台売れるんだよ」って話になる。
でも個人経営の町工場なら「年間5台売れれば食える」わけです。「昭和のてんとう虫を現代技術で蘇らせたい」っていうマニアが少数でも存在すれば、それで十分成り立つ。
つまり:
- 大企業: 「市場が小さすぎる」「採算合わない」で切り捨て
- 零細企業: 「誰も競合しない独占市場」として成立
同じ商品・サービスでも、事業規模によって「やる価値があるかどうか」の判断が180度変わる。零細企業のターゲティングは「効率化」じゃない。「大企業が来ない場所で勝つ」戦略なんです。
だから零細企業が「幅広いターゲットに訴求しよう」なんて考えたら自殺行為。大企業の土俵で勝負してどうするんですか。
でも「絞りすぎ」も危険。現実的なバランスの見つけ方
ただし、ここで注意が必要なのは「絞れば絞るほどいい」って訳じゃないってこと。
さっきのクラシックカーEV化だって、本当に「スバル360のEV化だけ」に特化したら、市場が小さすぎて食っていけないかもしれない。実際は「昭和の軽自動車EV化」とか「国産クラシックカー全般のEV化」みたいに、ある程度幅を持たせる必要がある。
零細企業のターゲティングで重要なのは、この「絞り加減の見極め」です:
- 上限ライン: これ以上広げると大企業と競合して負ける
- 下限ライン: これ以上狭めると売上が立たなくて食えない
- スイートスポット: その間の「大企業が来ないけど、食える」範囲
例えば地元のカフェなら:
- ❌ 広すぎ:「コーヒー全般」→ スタバと競合
- ❌ 狭すぎ:「エチオピア産ゲイシャ種のハンドドリップのみ」→ 客が月3人
- ✅ 適正:「シングルオリジンにこだわる大人のカフェ」→ ニッチだけど一定数いる
最初は少し広めに設定して、競合の動きや顧客反応を見ながら徐々に絞り込んでいく。これが現実的なやり方ですね。
理論通りに「とにかく絞れ」って考えてると、絞りすぎて市場を消滅させちゃう。
零細企業の最大の武器:「機動力」を活かした仮説検証
でも結局のところ、適正なターゲティングなんて「やってみるしかない」んですよ。
ただし、闇雲にやるんじゃなく、仮説→検証→改善のサイクルを高速で回す。これが零細企業の本当の強みです。
例えば、さっきのクラシックカーEV化。最初は「売る」つもりで始めたとします:
- 仮説: 昭和ノスタルジー+環境意識の富裕層に売れるはず
- 検証: スバル360を1台EV化してSNSに投稿
- 結果: 完成品より「作業工程動画」がバズった
- 軌道修正: 「売る」から「見せる」に戦略変更、YouTube収益に軸足
これ、大企業だったらどうなると思います?「クラシックカーEV化動画をやりたいです」って企画書作って、上司に説明して、役員会議にかけて、予算確保して…って、承認下りる頃にはブームが終わってる。
しかも途中で「投資対効果が見えません」「ブランドイメージへのリスクは?」とか言われて、結局無難な企画に変更されちゃう。
でも零細企業なら:
- 朝「面白そう」と思う
- 昼にはもう作業開始
- 夕方にはSNSに投稿
- 翌日バズってたら「よし、これで行こう」
この機動力こそ、大企業には絶対真似できない零細企業の武器です。
だから零細企業の4Pは「完璧に計画してから実行」じゃない。「小さく実験しながら軌道修正」が前提になる。従来のマーケティング理論とは、根本的に考え方が違うんです。
まとめ:理論は道具、時代と事業規模に合わせて使え
結局何が言いたいかって、コトラーが悪いわけじゃないんですよ。4PもSTPも、枠組みとしては今でも十分使える。
ただし「使い方」を間違えたらダメ。
1960年代の成長期理論:
- 目的:効率化(どうやって大量に売るか)
- 前提:作れば売れる市場
- ターゲティング:広告費の効率化のため
2025年の零細企業現実:
- 目的:生存戦略(どうやって生き残るか)
- 前提:競合だらけの成熟市場
- ターゲティング:勝てる土俵を見つけるため
この違いを理解せずに、60年前の理論をそのまま現代の零細企業に当てはめようとするから失敗する。
特に零細企業の場合、机上の完璧な戦略より「小さく始めて高速で軌道修正する機動力」の方が重要。大企業が2年かけて検討してる間に、10回実験して答えを見つける。これが現代の勝ち方です。
理論は神様じゃない。時代背景と事業規模を理解して、自分の現実に合わせて使い倒す道具です。
コトラーに騙されず、でもコトラーを上手く使って、今日も生き残りをかけた実験を続けていきましょう。
春日井でAI・DX相談やってます → Room8公式サイト
この記事が役に立ったら → note でフォロー