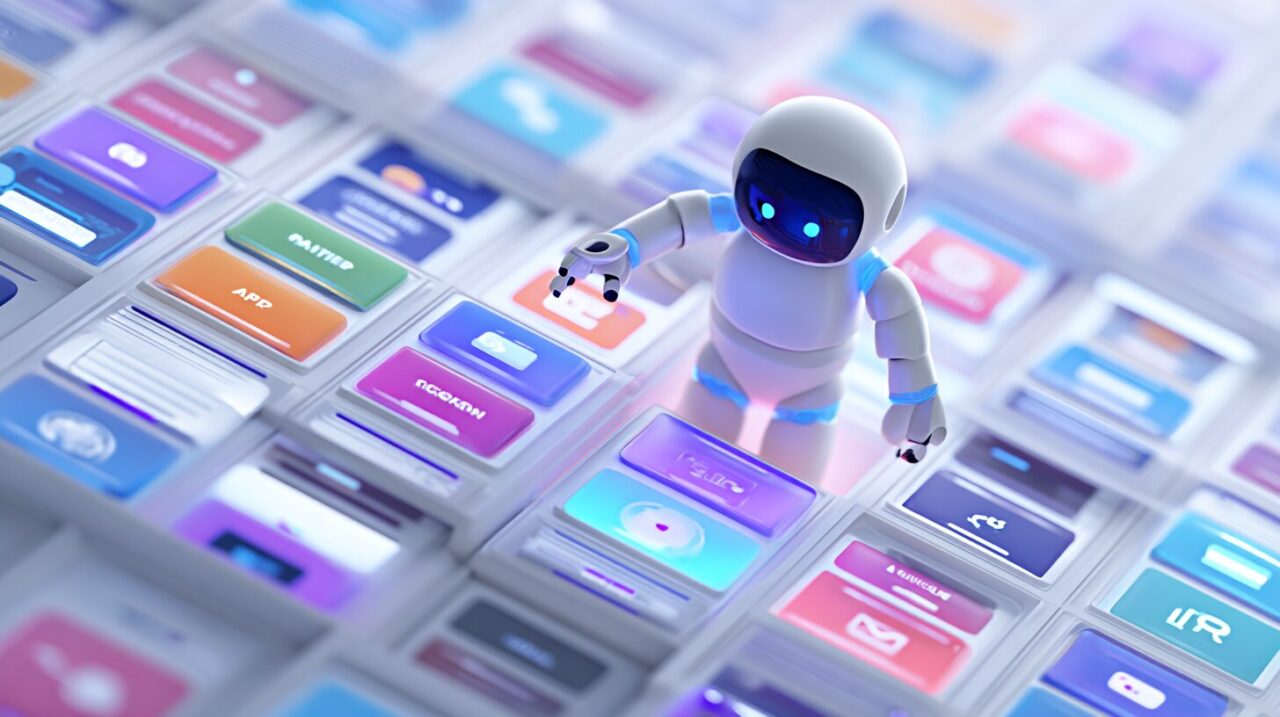こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です。
最近「GAS書くのそろそろ限界かもな」って思いながら、また新しい仕様に合わせてスクリプトを直してるそこの君。
悪いことは言わない。今すぐMCPを知ったほうがいい。
僕らがこの10年、「Zapierでのルーティング」「Webhookの受け渡し」「APIの地獄構文」…そんな業務自動化の泥臭い連携に振り回されてきた中、ついに「ChatGPT連携」みたいな新しい波が来て——結局また別の沼が始まった。
今、ようやくAIが「本当の意味で外部ツールを使える時代」が来ようとしてる。
その中心にあるのが、MCP(Model Context Protocol)。
まだ聞き慣れないかもしれないけど、これが分かってないとAI活用の話、ほとんど“過去の文法”になる。
MCPとは何か?
Model Context Protocol=AIとツールを繋ぐ“共通語”
ざっくり言うと、MCPは「AIが道具を使うための標準インターフェース」。
もっと言えば、どのAIでも同じ形式でツール(APIやアクション)を使えるようにする共通語のことだ。
いままでは、ChatGPTにはFunction Calling、ClaudeにはTools API、GeminiにはExtensions…と、AIごとに“独自の道具の使い方”があって、開発者はそのたびに仕様を読み、コードを分岐させ、ツールを複製してきた。地獄だった。
MCPはこのカオスに終止符を打つ。
OpenAI、Anthropic、Google、さらにはStripeやCloudflareまで巻き込んで、
「ツールとAIの間に共通プロトコルを入れようぜ」という合意ができたのが、2024〜2025年にかけての大きな転換点だ。
この共通語を喋れるツールサーバー(MCP Server)さえ用意すれば、あとはどのAIか
そもそも、何が問題だったのか?
それぞれ勝手に作ってた「独自のツール連携」
自動化好きな人間なら、みんな一度は思ったはずだ。「なんでこんなにバラバラなのか?」
Zapierでルーティングしても、Webhookの仕様で詰まり、APIの“地獄構文”で夜中にエラーが出る。「また仕様変更かよ」と呟きつつ直す日々。
そして時代が進み、ChatGPTやClaude、Geminiみたいな“AIとツールの連携”がやっと現場に降りてきた——と思いきや、
今度は「AIごとに連携仕様が全部違う」っていう新たなカオスが爆誕。
ChatGPTのFunction Calling地獄、ClaudeのTools API、GeminiのExtension沼
- ChatGPTにはFunction Calling。
- ClaudeにはTools API。
- GeminiにはExtension。
どれも「AIが外部ツールを呼べる!」という看板は同じだけど、結局“AIごとに全部別物”。
ツールを作る側は、そのたびに「このAI専用の仕様」に合わせて実装し直し。
実際、Function CallingのJSONを組んで「やれやれ今度はGPT用…」と思ったら、Claude用はまた別ルール。
Gemini用にExtension作ろうとしたら、「Googleアカウントでしか動かん」とか出てくる。
要するに、全部「個人商店の専用端末」みたいなもん。
ユーザーも開発者も振り回される地獄が繰り返されてきた。
「ツールがAIに合わせなきゃいけない」不毛な構造
この構造、冷静に考えると終わってる。
本来、「AIごとに別の仕様を実装して下さい」なんて、
コストしか増えない上に、進化の足枷にしかならない。
現場は「AIにツールを使わせたい」だけなのに、
“どのAIからも呼べる”ようにしようと思ったら、全部バラバラに実装・メンテ・テスト。
地獄だ。
MCPがもたらす“革命”
「APIの面倒な仕様合わせを、AIが勝手にやる」世界
API連携って、結局は「相手(API)の仕様に完璧に合わせてデータを送る」ことがすべてだった。
普段やってた“APIの仕様書を読み込んで、求められるJSON形式やデータ型に変換して…“
あの激烈に面倒くさい部分が自動化される。それがMCP。
MCP対応のAI(=そのAPI専用の仕様を“丸ごと記憶したAI”)が間に立つことで——
- 「人間が適当に入力したデータ」も
- 「他のAIが適当に加工したデータ」も
全部、“正しいAPI仕様”に自動で変換してくれる。
だから、「これ、Stripeで決済して」「この予定をカレンダーに追加して」みたいなざっくり指示を出すだけで、
MCPサーバーが“裏で”全部仕様通りに整形してAPIに渡してくれる。
AI同士・サービス同士のやりとりもスムーズになる
いままでだと「このAIで作ったデータは、あのAPIじゃ通用しない」とか、
「人力で“APIごとの仕様”に直して投げ直す」みたいな無駄が山ほどあった。
MCPだと、“意図”だけ伝えれば、あとはAIが全部つなぎ直してくれる。
- どんなAI同士でも
- どんなサービス同士でも
「データの仕様が違う問題」から人間が解放される。
つまり、“APIの面倒を全部AIに押し付けて自動化できる”時代
もはや、APIの仕様に人間がビクビクする時代は終わり。
「やりたいこと」と「そのAPIがどう受け取りたいか」の間を全部MCPが吸収してくれる。
だから現場は、「仕様書とにらめっこ」から卒業して、
「やりたい業務フロー」をAIとMCPに丸投げすればいいだけ。
プラグインとは何が違うのか?
ChatGPT Pluginは“店の棚”、MCPは“裏口の道具箱”
「プラグイン?また新しい呼び方か」と思ったそこのあなた。
確かに一時期、ChatGPT PluginだのGemini Extensionだの、“AIに便利ツールを生やそう”ブームはあった。
でも、あれは結局“表面だけ”取り繕った仕組みだった。
プラグイン方式:
- 「このAI用です」っていう“専用端末”を作って
- “棚に陳列”して
- “誰かがクリックして使う”ものだった
つまり、「この道具を使いたいならこの棚に来い」という昭和スタイル。
MCP方式:
- 「AIが“好きな時に好きなツール”を裏口から引っ張り出す」
- “人が使う”んじゃなく、“AI自身が自分で道具箱から選ぶ”
- しかも、「どのAIでも」「どんなAPIでも」全部共通語でつなげる
昭和の陳列棚から、令和の自動工具倉庫にアップグレードした感じ。
表面的なおもちゃ→本物のAPI連携へ
プラグインは「面白いデモ」や「限定的なサービス」では使えた。
でも、本気で現場の業務を自動化したい/AIを“働かせたい”なら、
全部のツールと“本物のAPI連携”ができないと意味がない。
MCPはその“裏方”として、AIが「現場の道具」と本気でやり取りできる世界を作る。
もはやプラグインごっこの時代じゃない。
“本番運用”を見据えた本物の自動化インフラ——それがMCP。
MCPが見せる“自動化の未来”
現場が勝手に動く。cron + MCP + エージェントの世界
いままでは「人が指示して、AIが答えて、APIを手作業で叩いて」——この繰り返し。
でもMCPがあると、cronやWebhook、CLIからトリガーが飛ぶたびに、AIが“裏方で全部勝手に処理”するのが当たり前になる。
- 決済フローも
- データ集計も
- 日報作成も
- 問い合わせ返信も
全部、AIエージェント×MCPサーバーが自律的に回すだけ。
これから業務設計で「MCP対応してるか?」が死活問題に
近い将来、「このサービス、MCP対応してます?」がAPI選定の第一条件になる。
「うちは独自APIです」なんて言ってる会社、いずれ化石扱い。
開発側も運用側も、「APIの仕様を一つずつ覚えて人力で変換」なんてやってられない。
“現場の自動化”が現実になる時代、 MCPを無視したツールやサービスはどんどん置き去りになる。
MCP+エージェントによる自動化、
「気付いた者から先に“人間の業務”を減らしていく世界」
さぁ、いつまで手作業と仲良くしてます?
FAQ
MCPとは何ですか?
MCP(Model Context Protocol)は、AIとツールを繋ぐ共通のインターフェースであり、どのAIでも同じ形式でツールを利用できるようにするためのプロトコルです。MCPが解決する問題は何ですか?
MCPは、AIごとに異なるツール連携仕様を統一し、開発者が個別に実装する必要をなくします。これにより、ツールとAIの連携が簡素化され、開発コストと複雑性が削減されます。なぜAIごとに異なるツール連携仕様が問題だったのですか?
AIごとに異なるツール連携仕様が存在することで、開発者はそれぞれのAIに合わせて個別に実装・メンテナンスを行う必要があり、これが開発の負担を増やし、効率を下げていました。MCPはどのようにAPI連携を簡単にしますか?
MCP対応のAIがAPIの仕様を記憶し、入力されたデータを自動で正しいAPI仕様に変換します。これにより、開発者が個別のAPI仕様に合わせてデータを変換する必要がなくなります。MCPの導入による業界の変化は何ですか?
MCPの導入により、AIとツールの連携が標準化され、開発者の負担が軽減されるとともに、AIの活用がより広範囲に可能となります。これにより、業務自動化の効率が向上し、AI技術の進化が加速します。まとめ
MCP(Model Context Protocol)の登場で、「APIごとの面倒な仕様合わせ」に延々つき合わされる時代は本格的に終わる。
ChatGPTだろうがClaudeだろうがGeminiだろうが、「ツール連携のたびに仕様と格闘→コピペ地獄」という10年以上続いた惨劇に、ようやく終止符が打たれる。
今や「やりたいこと」をざっくりAIに伝えるだけで、MCPが裏でAPI仕様通りに勝手に変換し、全部丸投げで自動化が進む。
プラグインごっこやExtension地獄みたいな旧世代の“おもちゃ遊び”はもう不要。
AIは現場の裏方として本格参戦し、cron・Webhook・CLIと組み合わせて「人間が知らないうちに仕事が片付く」世界が、いま現実になりつつある。
MCPを知らずにAI自動化を語るのは、ガラケーでiPhone時代をドヤ顔で論じるのと同じ。
今この瞬間から、「MCPに対応してる?」がAPI設計も業務自動化も新しい常識になる。
- OpenAI公式MCP解説(英語)
- Anthropic MCP発表記事
- Google Gemini MCP公式ドキュメント
(ここは全員一度は絶対見ておくべき)
実際、コワーキングの現場で毎日顔を合わせるエンジニアたちも、
「AIで業務が根本から変わる時代が来る」と頭では分かってる。
でも「まだ当分は自分の仕事には関係ないだろうな」と思ってる人が大半だ。
現実は今日もエディタを開いて、API仕様書をにらみながらコードを書いてる——そんな毎日を送っている。
MCPなんて言葉はもちろん聞いたこともない、というのが普通。
だけど、こういう“時代の転換点”こそ、知ってるかどうかで「面倒な作業から抜け出せるか、いつまでも手を動かし続けるか」が決まる。
今ここで一歩先を見ておかないと、次の波は確実に乗り遅れるかな?って思ってる。