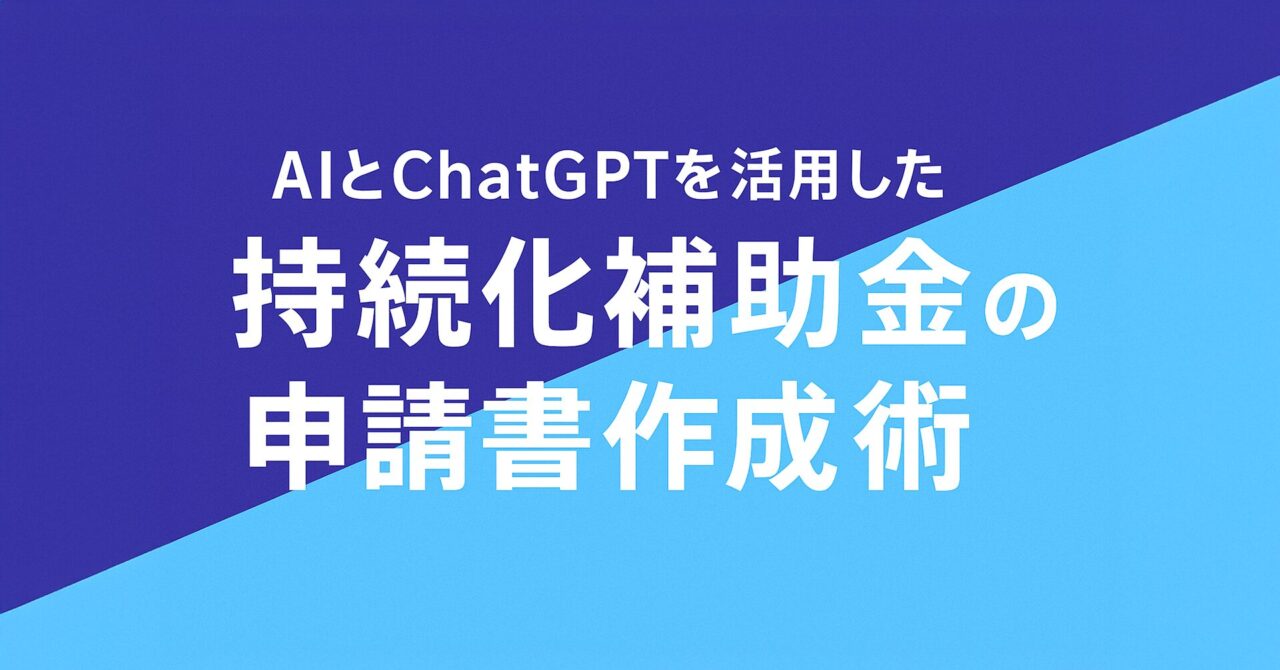こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です!
最近は名古屋・春日井エリアでAIコンサルもしてまして、
「ChatGPTで補助金申請書を作りたい」なんて相談も増えてきました。
実は僕自身、これまで何度も小規模事業者持続化補助金の採択を勝ち取ってきた経験があります。
一番最近だと、第14回(2023年12月ごろ)の採択。
この時は、今ほど賢くなかったChatGPTを“無理やり使い倒して”何とか書き上げました。
それ以前の2020年も採択、その前も(年は忘れたけど)合格。
――要するに、補助金“ガチ勢”です。
さて、今年もやってきました“補助金シーズン”。
毎年「とりあえずコピペで出しておけば何とかなるっしょ」って人を見かけますが、
はっきり言って、その発想だと審査員から「また来たか…」とため息しか出ません。
どうせなら“本気で自分のビジネスをブラッシュアップできる書類”に仕上げませんか?
今回は「ChatGPTを使って、ただの作文を“採択される申請書”に進化させるための詰め方」を、
Room8流のちょっと辛口な視点で徹底解説します。
「ChatGPTで書類作ったら通るでしょ?」なんて甘い夢を見てる人、
むしろここからが本当のスタートです。
どうせやるなら、“審査員に一目置かれるレベル”まで詰めてみませんか?
では、いきましょうか。
採択される申請書の全体像と構成

まず、補助金の申請書って、ただ「やりたいこと」を書くだけの作文じゃありません。
僕も何度も書いて通してきて思うのは、「審査員に“納得感”を持たせるストーリーになっているか?」が最重要だということ。
補助金の審査員は、必ずしもその業界のプロじゃありません。
むしろ“事業計画書を読むプロ”です。
つまり、事業の細かい現場よりも、「この会社はちゃんと考えて経営してるな」と思えるかどうか――そこが勝負の分かれ目です。
申請書で押さえるべき流れ
- 現状分析(自社の強み・課題・業界や市場動向)
いきなり夢や希望を語る前に、「今うちは何が強みで、どんな課題を抱えていて、業界はどんな状況か」を整理。
ここで“なるほど”と思わせれば、後の流れも説得力が増します。 - ビジョン・目標
単なる売上アップだけじゃなく、「どうしてその目標を立てたのか」「その先にどんな価値を作りたいのか」まで一歩踏み込む。
社会的意義や地域との関係性をセットで語ると、他と差がつきます。 - 具体的な取組内容・事業計画
ここが一番の“肉付けポイント”。
「なぜその施策が必要か」「現状の課題とどう結びついているか」「どこまでを補助事業でやるのか」――筋が通ったストーリーに。 - 生産性向上の取組(あれば絶対入れる!)
小規模事業こそ“効率化”や“新しい仕組みの導入”は超アピールポイント。
例:IT導入、業務の自動化、スタッフ教育など。ここはこじつけでも何か盛っておくと採択率が大きく変わる。 - 効果・KPI・成果予測
売上・利益だけじゃなく、「新規顧客数」「リピート率」「業務効率化」など、できるだけ数字で語るのがコツ。
ここがフワッとしてると“ただの夢物語”で終わるので要注意。 - 加点要素(賃金引上げ・女性/若手経営・承継・経営力向上etc.)
“加点欄”に書くだけじゃ弱い。ストーリー全体の流れの中で「ウチはこういう背景で取り組んでます」を自然にアピールできると強い。
まとめると――
「審査員が“なんとなく良さそう”と思える一貫した流れ」「加点ポイントは全体にちりばめる」「生産性向上はできるだけ捻出する」
これが、ただの作文と“通る申請書”の大きな差です。
次は、この流れをどうChatGPTに落とし込むのか?に進みます。
OKなら、続けていきます!
ChatGPTで作る申請書 ~「AI×人間」二人三脚で磨き上げる~
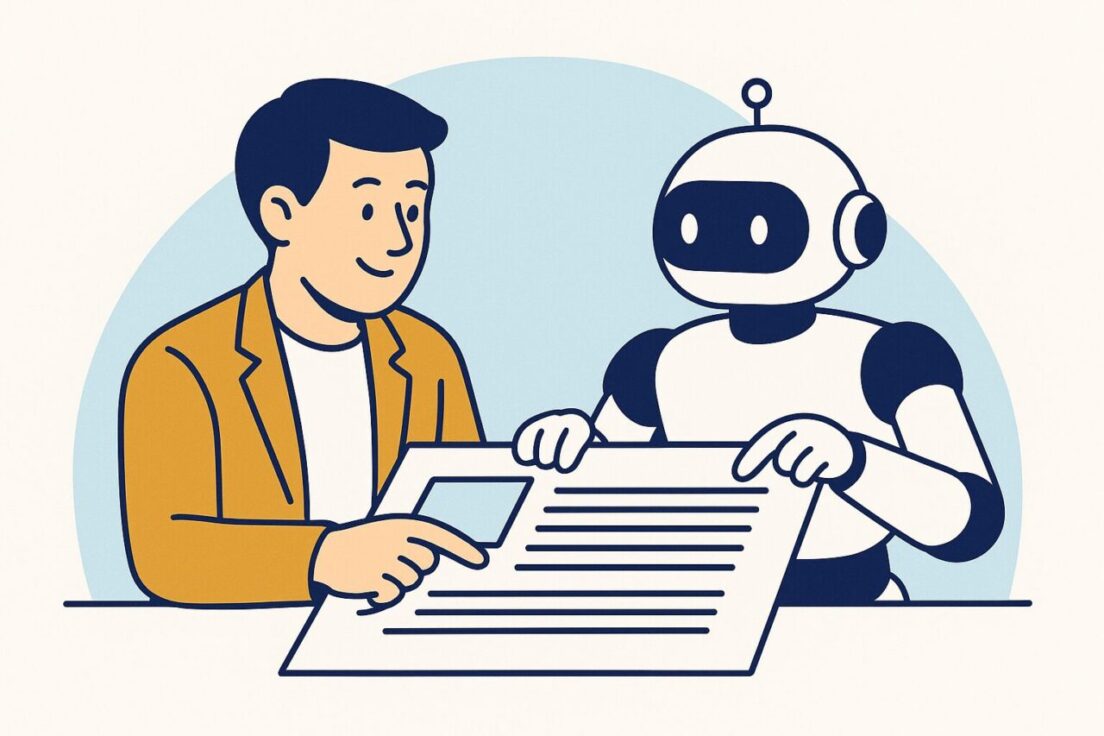
最近よく「ChatGPTに補助金申請書を書かせました!」という声を聞くけど、
実際に通るかどうかは“AIと自分がどれだけ二人三脚でブラッシュアップしたか”で大きく変わる。
ChatGPTは“型”にハメてそれっぽい下書きはすぐ出してくれる。
でも、そのまま提出するのは、漫画でいえば「ネーム(下書き)」の段階。
ここから先が本番――
編集者(=自分)が「このストーリーだと弱い」「もっとここ深堀り」「読者=審査員がどう思う?」と、
何度もツッコミ&提案しながらAIにリライトを繰り返させる。
そうやって“共作”していくのが本当の意味でのAI活用。
最初はベタ打ちでもOK。
大事なのは「ここが足りない」「この表現もっとこうしたい」と遠慮なく“ケチをつけて”どんどんブラッシュアップしていくこと。
僕が普段ChatGPTにやってるみたいに、「お前、まだ甘いぞ!」とツッコミ倒すのが一番いい使い方。
よく「AIはあくまで道具」なんて言われるけど、僕の感覚だと「漫画家と編集者が共同で作品を作る」感じに近い。
原作(事業の現場)は自分、でも作画(草案や構成)はAI、編集(最終クオリティ)は自分――この往復こそ最強のチーム。
それと、たまに「AIで書いた申請書って通るの?」って心配する声も聞くけど、
正直、補助金は運の要素もかなり大きい。
しっかり書いても落ちることは普通にあるし、逆に「あれ?」って内容が通ることもザラ。
だからこそ、“確率を1%でも上げる作業”だと割り切って、
「AI×自分の二人三脚」で仕上げていくのが一番合理的だと思うんです。
ChatGPTを“ただの下書きマシン”で終わらせず、
「AI×自分の二人三脚」で申請書のクオリティをとことん高める――
それがRoom8流の勝ちパターンです。
分割&詰めで一気に質が上がる
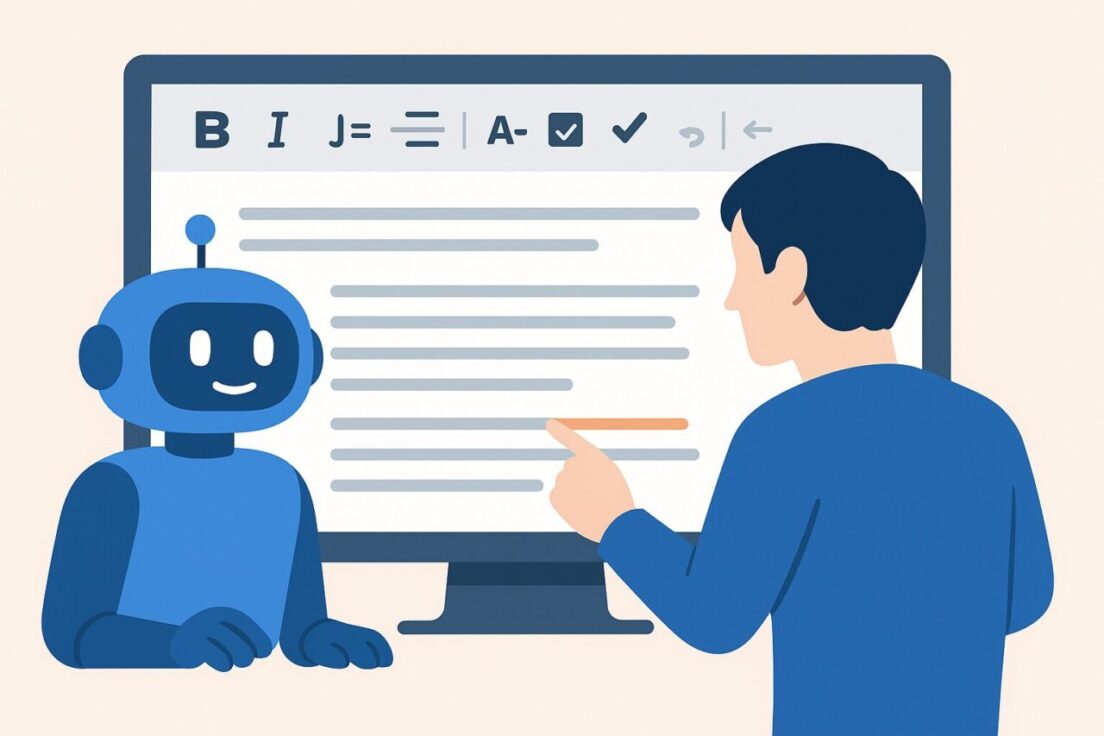
補助金申請書や長文記事をAIで書こうとすると、多くの人が「とりあえず全部まとめて一気に書かせて終わり!」となりがち。でも実際やってみると、これが一番薄っぺらくなります。
じゃあ、「薄いな」と思って分量を増やそうとすると…
今度は逆に、AIは“絶妙なボリューム”で増やすのが苦手で、長すぎたり短すぎたり、なかなか狙った感じになりません。
僕もいろいろ試してきて思うのは――
「1テーマをまず細かくサブセクションに分けて、AIに一つずつ出力させる」
これがベストなやり方です。
たとえば「自社の概要」ひとつとっても、
- 事業内容
- 経営課題
- 売上の推移
- ビジョン
…みたいに項目を細かく分けて、それぞれAIにしっかり膨らませて書かせるのが理想。
ただし、1セクションにつき最大4000文字というルールがあるので、
「項目が4つなら、一つあたり1000文字以内」
「6つに分けたなら、一つあたり600文字ちょっと」
…みたいに、最終的には“合計で上限を超えないように”分量調整が必要。
「ここは絶対削れない!」という項目はそのまま盛って、
他の部分で少し圧縮するなど、全体のバランスを人間が“現場判断”で整えるのがコツです。
この方法なら、「盛りたいだけ盛って、後で調整」という一番コントロールしやすい書き方ができます。
実際、「1000文字で」と指示してもAIはその通りに書けません。
短文だったり、逆にくどい長文だったり――。
だから“内容を見ながら、ここはもっと膨らませて、ここは削って”と、人間側が都度ジャッジしながら追加・修正していくしかないんです。
この「編集者マインド」で、加点できるポイント・社会貢献・小さな強みまで、該当しそうなら“全部盛る”のが大正解。
「これぐらいでいいか」と遠慮する必要はゼロ。
補助金の世界は“書かれていないこと=存在しない”のと同じ。
もったいない精神より、盛りすぎぐらいがちょうどいい。
最終的には、
- 全体アウトラインを作り、サブセクションに分ける
- AIでひとつずつ出させて、毎回「もっと盛れ」「具体例増やせ」と編集者魂で詰めていく
- 分量や密度は“手動で”何度も調整
- 全体を読み直して「違和感」「一貫性」「加点盛り」を総点検
こうして仕上がった申請書や記事は、一発出しの“量産型AI作文”とは説得力も熱量も段違いです。
AIはあくまで爆速の“下書き屋”+“共同編集者”。 本気で勝負したいなら「細かく分割&全部盛り&人間主導の調整」こそ最強。
次は、補助事業を“生産性向上”につなげる設計に進みます!
生産性向上の欄は任意?…でも絶対に書け

補助金申請書の中でよく出てくるのが、「生産性向上の取組(あれば)」という“任意”の項目。
ここ、ぶっちゃけ「書かなくても通ることはある」。
だけど僕は声を大にして言いたい――「書けるなら絶対に書いておけ」と。
なぜか?
この「生産性向上」というキーワード、審査員から見ても“将来伸びそうな会社”の証明になるし、加点ポイントにもなりやすい。
しかも、中小企業診断士や補助金コンサルに書類を見てもらうと、ほぼ100%「ここは何か書いて!」と指導が入る、“プロなら全員知ってる裏加点欄”だから。
ポイントは、普段の努力を書くのではなく、「今回の補助事業によって、どこがどう効率化・高度化されるか?」をハッキリ書くこと。
つまり、「新しい設備を入れることで手作業が自動化される」「AIやITツールで問い合わせ対応や事務作業が効率化する」「ホームページ制作で予約や発注の手間が減る」みたいに、“補助事業の効果=生産性アップ”と直結させるのがコツ。
「そんなの思い浮かばない」と感じる人も多いけど、
今はAIという最強の相談相手がいる時代。
ChatGPTにこう聞いてみてほしい。
「今回の補助事業で、うちの事業や業務のどこが“生産性向上”に当たるか、可能性を洗い出して」
すると、
- ホームページ制作 → 問い合わせや予約の自動化
- 新設備導入 → 作業時間の短縮
- AI・ITツール → 人手作業を自動化、情報共有の効率化
- 業務フローの見直し → 無駄な工程や人的ミスの減少
…など、自社の状況や申請内容に沿って“生産性向上ポイント”がいくつも出てくる。
大事なのは、AIと一緒に“自社にしか書けないポイント”を発掘して、それを自分の言葉で盛ること。
最初はピンとこなくても、「こういう効果はある?」「この部分も効率化につながる?」とAIに追加質問を重ねていけば、
本当にアピールできる要素がどんどん見つかります。
この「生産性向上」欄は、“任意”だからと省略しがちな人が多いけど、
書ける人だけが最後に1%分の合格チケットを掴む場所。
迷ったらAIに相談、それで十分。
このひと手間が、最後の合否を分けることも多い。
「確率を1%でも上げるためのひと手間」。
任意欄こそ、AIを使って“全部掘り出して盛る”。これがプロの申請書。
次は、採択率を上げる「加点テクニック」大全に進みます!
採択率を上げる「加点テクニック」大全

補助金の申請書には、「加点ポイント」という欄がありますが、ここは4000字フルで語るような場所ではありません。
該当している場合は必ずチェックして申告する――それだけでOK。
下手に盛りすぎるより、「当てはまるなら忘れずに伝える」ことが大切です。
代表的な加点ポイント(該当すればチェック!)
- 賃金引上げの取組
→ 従業員がいて賃金アップ予定なら、指定の欄にチェック+簡単な説明 - 女性・若手経営者
→ 経営者が女性または35歳未満なら、忘れず該当欄にチェック - 事業承継・第二創業
→ 世代交代や事業承継が絡む場合もチェック - 経営力向上計画の取得
→ 取得済ならラッキー、なければスルーでOK - 地域資源活用・地域貢献
→ 地元ネタや地域活性化に関わるなら記載 - インボイス登録
→ インボイス登録済の場合は忘れず記載
「ウチは該当しない…」という人も多いですが、ここは“できる人だけボーナス”くらいのイメージ。
逆に「該当しているのに書き忘れ・チェック忘れ」が一番もったいない。
チェック漏れに注意!
- 申請書全体のストーリー中で何度も触れる必要はなく、「加点項目」として“ちゃんと記載”しておくことが大事。
- ChatGPTにも「加点項目を見落とさないように一覧化して」と指示を出して確認すると安心。
- 忘れずに“伝える・チェックする”だけで、申請全体の印象も変わります。
加点ポイントは、「盛る」のではなく“拾い漏らしをしないこと”が全て。
該当すれば必ず書く、スルー厳禁。
ここを抑えておけば、無駄な減点を防げます。
次は、仕上げ・審査員に「分かってる感」を伝える最終調整へ進みます!
まとめ
ここまで「AI×分割×全部盛り」の申請書ブラッシュアップ術をお伝えしてきましたが、
最後にもうひとつ大事なことを言っておきます。
世の中には“補助金コンサル”と名乗って書類丸投げで8万とか10万とか取る業者も多いですが、
正直、それだと“自分で書ける力”も“ビジネスをブラッシュアップする感覚”も身につきません。
僕は春日井Room8のオーナーですが、最近はAIコンサルもやってます。
「AIと一緒に書類を詰めてみたい」「自分の言葉で申請書を仕上げたい」――
そんな人のためなら、AIコンサルは2万円でやってます。
(もちろん“補助金書類丸投げ作成”はやりません。あくまで“AIを使った壁打ち・自走サポート”です)
申請書は、ただ通ればいいわけじゃない。
せっかくなら「もらった後も胸を張れるレベル」まで仕上げて、
事業も自分自身も一段ステージを上げてやりましょう。
- ChatGPTやAIは“ただの時短道具”じゃない
- 分割・全部盛り・加点チェック・現場目線の詰め――
- これ全部、“AIと自分の二人三脚”で必ずできる
どうせやるなら、
「補助金でラクする」のではなく、「補助金で自分も事業も成長させる」
そんなスタンスで攻めてみませんか?
困ったら、Room8で一緒にAI作戦会議やりましょう!