こんにちは、春日井コワーキングスペースRoom8オーナーの鶴田です。
AIがAPIを直接操作するだとか、MCP(Model Context Protocol)で業務自動化がもっとシンプルになるだとか、最近そんな話をよく見かけます。実際、AIまわりは毎年のように「次の当たり前」がアップデートされていきますが、現場で作業している身としては、その変化をどこか淡々と眺めているところもあります。
とはいえ、2024年から2025年にかけてAnthropicがMCPを「未来のスタンダード」として発表した当時、僕もAIとGASを組み合わせて“こんなことができたら面白いな”と、素直な好奇心から手を動かしていました。
実際、当時の実験記録も残っていますが、コードを書きながら「そのうちこういうのが標準になるんじゃないかな」と、ちょっと先取りして遊んでいた感覚です。
ちなみにMCPが何か気になる方は、公式の発表や開発者ドキュメント(Claude Code MCP解説)も参考にどうぞ。もう少し現場目線で噛み砕いたまとめとしては、自分でも「MCP(Model Context Protocol)とは何か?AI連携の“本質”を解説」を書いています。
要するに、AIに仕様書を投げてjsonの返事をGASで受けてAPIに渡す――そんな“好奇心の延長線上”でエセMCPをやっていたという話です。新しいものを試すワクワクは、どんな時代でも案外変わらないのかもしれません。
GASでエセMCPごっこしてた時代

MCPなんて便利な仕組みが存在しない頃、僕はGASとAI API(o4など)を組み合わせて、やりたい処理を全部プロンプトで説明し、AIに仕様通りのjsonを返してもらい、それをGASで各APIに投げる――そんな「エセMCPごっこ」を普通にやっていました。
今思えば、「AIに処理の手順まで考えさせて人間は指示だけすればいい」って発想自体は、MCPが後から公式に持ち出してきたものと本質的にはそう変わらない。
ただ、当時のGAS自動化は、あくまで人間が“AIの出力を咀嚼して”GAS側でロジックや例外処理を書き足して…と、間にやたら人力の工夫が入る。「AIがここまでやってくれるなら、あとはGASでなんとかしよう」みたいな泥臭さが残っていた。
でも、AI業界はそういう現場の工夫ごと一瞬で時代遅れにしてくる。
プロンプトエンジニアリングに夢中になればなるほど、
「すまん、その努力いらなくなった」とばかりにモデル自体が進化して、気付けば“プロンプト”そのものの意味も薄くなる。
GASでAIを使って自動化してたら、「今度はMCPで全部まとめて巻き取ります」と、公式から桁違いの仕組みが降ってくる。
気付くと、AIの進化スピードが人間の発想や行動をあっさり追い抜いていく。
自分なりに“最先端”を試しているつもりでも、数ヶ月後には全部AIに上書きされている。
それでも手を動かしているときのワクワクは、今も悪くないと思っている。
MCP登場で何が変わったか

MCP(Model Context Protocol)が公式に登場して、一番インパクトが大きかったのはここ。
「人間がAPI仕様や処理フローを頭ひねってGASで書く」 そんな時代が、いよいよ終わる。
MCPは、AIが“意図”を読み取った時点で、
APIの細かい仕様なんてものは自動で吸収し、裏でちゃっかり全部処理してくれる。
これまで現場で
「このAPIはこういう形式で…」
「プロンプトをこう調整して…」
と頭を抱えていた泥臭い部分――
そもそも、その苦労自体が不要になる。
現場感覚としては、
- まだ「この分岐だけ特殊」みたいな例外処理は残る
- すべてがノーコードで“理想通り”には回らない
…という保留はありつつも、
「AIが業務全体を理解して“流れ”を組み立てる」
この方向性はもう逆らえない。
実際、
せっかく自分で試行錯誤したのに、気付けばAIに上書きされている
でも、“面倒なこと”を手放せるなら、それはそれで悪くない
そんな、ちょっと複雑な納得感もある。
たぶん未来は、想像よりも速く
「人間が頑張らなくてもいい領域」が広がっていく。
“手で自動化を組む”経験も、そのうち「あの頃は苦労したね」と笑い話になる。
現場の知恵も、すぐ陳腐化する
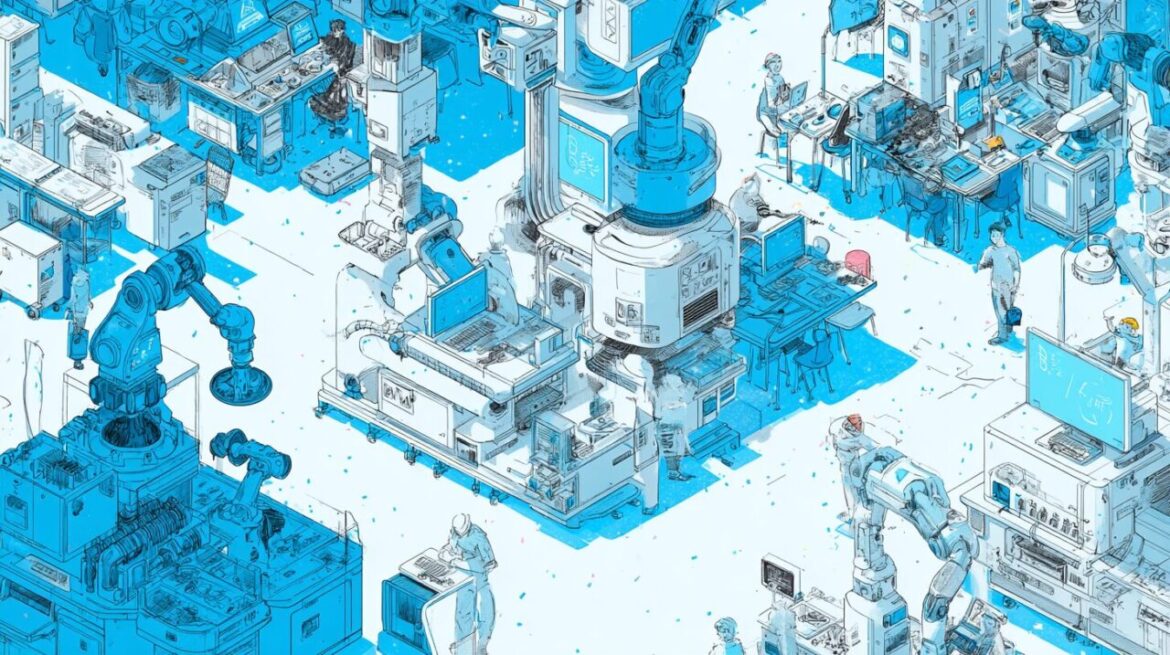
(横長イメージ:「AIがどんどん人間の工夫を飲み込んでいく、時間の流れを描いたイラスト」→skill-obsolete-timeline.jpg)
面白いのは、現場で手を動かして得たノウハウも、“知見”も、
AIの進化速度の前ではどんどん色褪せていくという現実。
今この瞬間は、「自分の方が一歩先を行っている」と感じられても、
1年も経てば、ほぼ確実にAIにごっそり追い抜かれている。
むしろ、「追い抜かれていく感覚」を体感できるのが現場の特権――いや、罰ゲームかもしれない。
実際、
世の中の大半はまだそこまでAIの“最新”に付いてきていない。
だから今の自分たちには、「現場の役割」や「先回りして案内する価値」が残っているだけ。
でも本質的には、
現場の細かいスキルやノウハウは、“陳腐化する運命”にあると思う。
となると――
これからは、
「手段やスキル」ではなく「目的そのもの」にどれだけ迫れるか
が問われてくる。
- この自動化は何のため?
- 誰がどこでどう使うべきか?
- そもそも“価値”はどこにあるのか?
結局、“手段の最先端”はAIが全部塗り替えていく。
けれど、AIには“目的”がない。
目的は、いつだって人間側から与えるしかない。
どんなにAIが進化しても、
「何をしたいか」だけは、結局自分で決めるしかない。
その“目的”をどう見つけてどう育てていくか――
そこにしか、人間側の余地は残っていない気がしている。
FAQ
GAS自動化とMCPの違いは何ですか?
GAS自動化は人間がAIの出力を基にロジックや例外処理を手動で追加する必要がありますが、MCPはAIが意図を読み取り、APIの細かい仕様を自動で吸収し、処理を行うため、手動での介入がほとんど不要です。MCPが登場して何が変わったのですか?
MCPの登場により、人間がAPI仕様や処理フローを考えてGASで書く必要がなくなり、AIが業務全体を理解して流れを組み立てることが可能になりました。これにより、従来の手作業が不要になり、業務自動化がよりシンプルになりました。MCPとは何ですか?
MCP(Model Context Protocol)は、AIが業務の意図を理解し、APIの仕様を自動で吸収して処理を行うプロトコルです。これにより、業務自動化が容易になり、従来の手作業を減らすことができます。AIの進化はどのように人間の役割を変えていますか?
AIの進化により、人間が手動で行っていたプロンプトエンジニアリングやAPI仕様の調整が不要になり、AIが業務全体を理解して自動化することが可能になっています。これにより、人間はよりクリエイティブな業務に集中できるようになります。MCPでの例外処理はどのように行われますか?
MCPでは、AIが業務全体を理解して処理を行いますが、特殊な例外処理が必要な場合は、まだ人間が介入する必要があります。ただし、全体的な流れはAIが組み立てるため、手作業は大幅に減少します。まとめ
(横長イメージ:「人間が“何をするか”だけを見つめている、静かなAI時代の一幕」→purpose-in-ai-era.jpg)
GASでエセMCPごっこをしていた日々も、いまやAIエージェント全盛であっさり過去の遺物になりつつある。
現場の手間やスキルは、AIの進化によってどんどん“どうでもよく”なっていく。
正直、「せっかく覚えたのに…」と脱力する瞬間も多い。
でも――
AIは、どれだけ進化しても「目的」そのものを持つことはできない。
手段はAIがいくらでも提供してくれる。
けれど、「なぜやるのか」「何をしたいのか」だけは、自分で決めるしかない。
AI時代の“現場”は、もうスキルの見せ合いでも、努力自慢でもなくなる。
必要なのは、「何を実現したいのか」を問い続ける力――
それだけが、たぶん最後まで残る人間らしさだと思っている。

